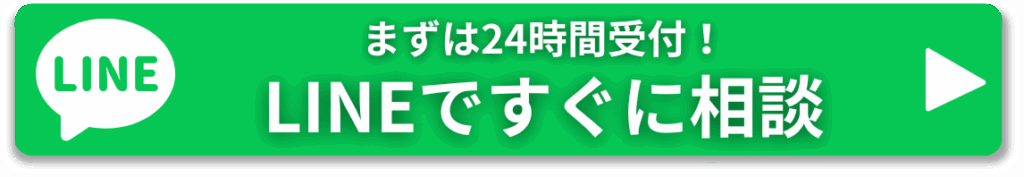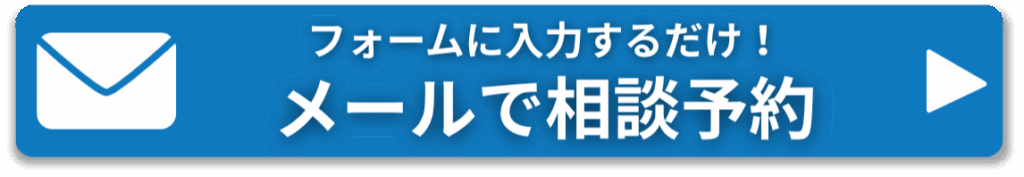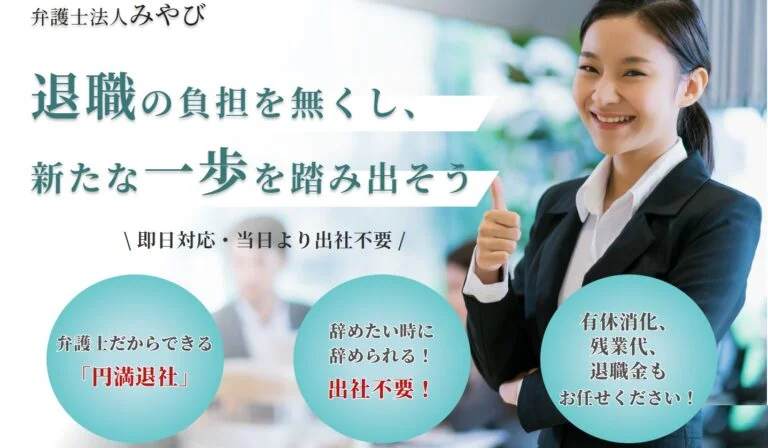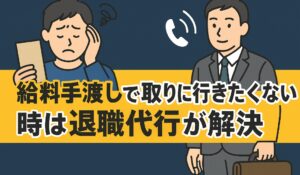退職代行のその後に待つリスクと対策、転職活動の注意点を解説
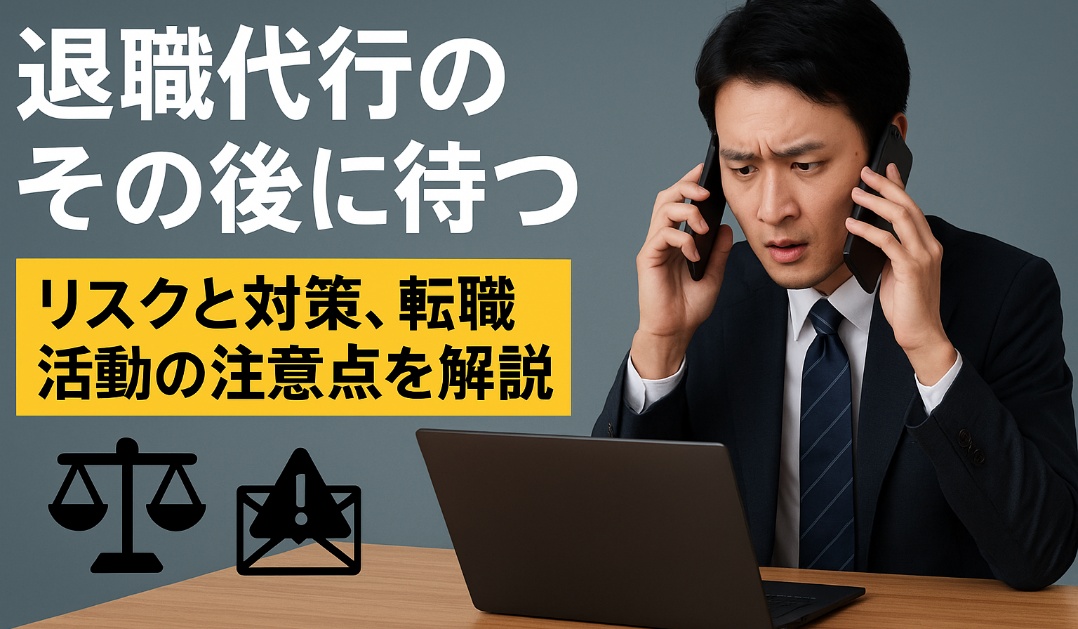
退職代行を使えば会社に直接連絡せずに退職できる便利さがありますが、その後には避けて通れない手続きやリスクが待っています。実際に利用した人の声を振り返ると「退職はできたが書類や貸与品の対応に困った」「会社から直接連絡が来て不安になった」といったケースも少なくありません。この記事では、退職代行のその後にどんな流れが待っているのか、注意点やリスクへの対策を詳しく解説していきます。
退職代行を利用:その後の流れを解説

退職代行を利用した後は、会社とのやり取りをすべて代行業者や弁護士が引き受けてくれます。ただし「退職が成立した時点で全て完了」ではありません。その後も貸与品の返却や離職票の受け取り、退職金や有給休暇の精算など、重要な手続きが控えています。また、悪質な会社によっては退職完了後に嫌がらせや賠償請求をしてくるところもあります。
これから退職代行の利用を検討している人は、まずは全体の流れを事前に理解しておくことが大切です。
退職代行申し込みから退職完了までの基本的な流れ
一般的な流れは以下の通りです。まず退職代行に申し込み、ヒアリングを経て会社へ退職の意思を伝達します。その後、会社は受理し、退職日や必要書類の調整が行われます。弁護士対応であれば未払い賃金や有給休暇の消化についても交渉してくれます。最終的に退職日を迎え、離職票や源泉徴収票が郵送されれば手続き完了です。退職届や引き継ぎ資料などは退職日までに作成を終えて、会社に郵送することになります。退職日を迎えてなにも問題がなさそうであれば、そのまま契約は終了となりますが、トラブルに備えて退職代行完了後のアフターサポート期間も考慮することは忘れてはいけません。
退職代行後に会社が直接連絡してくるケースと対応方法
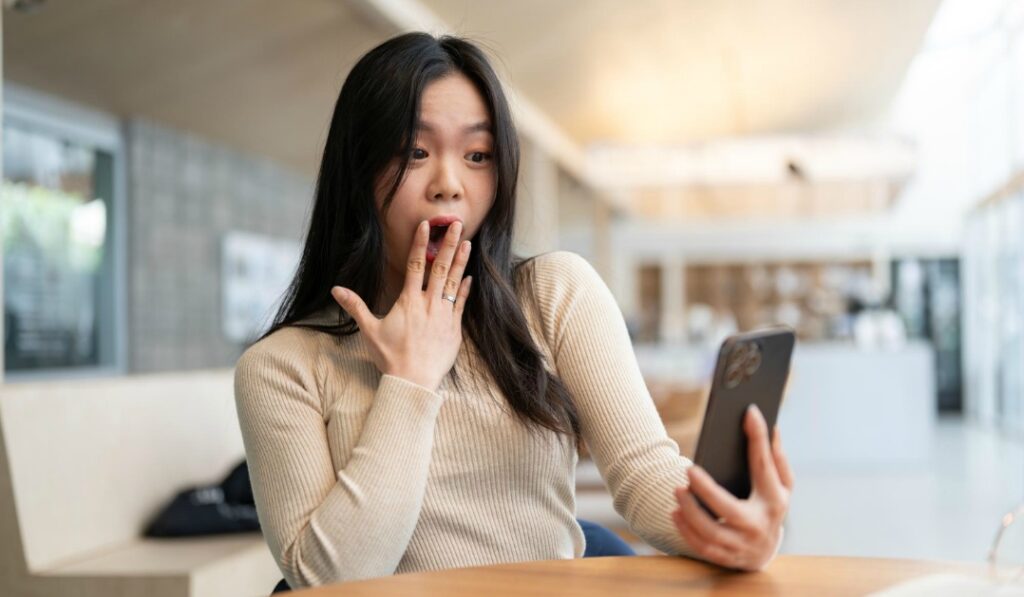
退職代行を使ったにもかかわらず「会社から直接電話やメールが来た」という声は珍しくありません。特に民間業者を利用した場合、会社が代行業者を無視して本人に連絡してくることがあります。こうした連絡は法的には不当ではありませんが、精神的に大きな負担になります。
弁護士型の退職代行を利用していれば、会社は代理人である弁護士を通じてしか連絡できません。万一直接の連絡があった場合も「代理人弁護士に連絡してください」と伝えるだけで済みます。民間業者を利用した場合は対応が難しく、不安を抱える人が多いため、最初から弁護士対応の退職代行を選ぶのが安心です。
退職代行のその後の貸与品返却・退職届提出の正しい手順

退職代行を利用した後でも、会社から借りているものや書類の提出は必ず必要です。ここを放置すると「返却がない」とトラブルの原因になりかねません。特に会社の備品や社員証、セキュリティカード、ノートPCなどの貸与品は速やかに返却する必要があります。また、退職届の提出を求められる場合もあり、形式を誤ると手続きが遅れることもあります。
退職代行利用後の貸与品返却リストと返却方法
貸与品には社員証、制服、PCやスマホ、会社印鑑、マニュアル、セキュリティカードなどがあります。返却は郵送で構いませんが、トラブル防止のため必ず書留や宅配便の記録が残る方法を選びましょう。弁護士対応の退職代行であれば返却方法も指示してもらえるため安心です。
退職届の提出タイミングと書類の書き方
退職代行を利用した場合でも、会社から正式な退職届を求められることがあります。一般的には退職日までに郵送すれば問題ありません。書き方は「退職届」と明記し、退職理由は「一身上の都合」とするのが無難です。間違っても「退職代行を利用した」とは記載しないようにしましょう。書類不備で退職処理が遅れるケースもあるため、早めの準備が大切です。
退職代行完了後の転職活動で注意すべき書類・手続きのポイント

退職代行で無事に会社を辞められても、その後の転職活動に必要な書類や手続きを整えていなければ不利になることがあります。特に離職票や源泉徴収票、雇用保険被保険者証などは次の職場や失業給付の申請に必須です。退職代行のその後は、まずこれらの書類が会社から送られているか確認しましょう。
退職代行その後の転職面接での説明方法と対策
転職面接では「なぜ前職を辞めたのか」と必ず聞かれます。退職代行を使ったことを正直に話す必要はありません。「体調不良で退職した」「家庭の事情で転職を決めた」といった面接官の気持ちが不利にならない無難な理由に置き換えるのが賢明です。近年はプライバシー保護の観点から、転職先が前職の職場に連絡をとるといったこともなくなりました。退職代行の利用を伝えることでマイナス評価につながる可能性があるため、面接では前向きな転職理由に焦点を当てましょう。
▶退職代行は転職に不利?利用時の影響と注意点を解説
退職代行完了。その後に発生するリスクと対策

退職代行を利用した直後は「辞められてホッとした」と感じる人も多いですが、その後に会社からの嫌がらせや損害賠償請求といったリスクに直面することもあります。これらを正しく理解し、事前に対策をとることが重要です。
退職代行その後の会社からの嫌がらせや報復行為への対処法
退職後に上司からの電話が続いたり、自宅に押しかけられるといった報復行為が報告されています。民間の退職代行業者では対応できないため、弁護士に相談し「連絡禁止の通知」を出してもらうのが有効です。放置してしまうと精神的に追い詰められたり、身内家族にも知られて家庭内トラブルに発展するケースもあるため、早めの対応が欠かせません。
退職代行後に損害賠償請求される可能性と対策
「突然辞めたせいで損害が出た」「研修費用を返せ」と会社から損害賠償請求を受ける事例があります。実際に裁判で認められるのは稀ですが、知識がないまま対応すると不安から支払ってしまう人もいます。また、前職から損害賠償請求されているうちは、転職活動もままなりません。弁護士対応の退職代行なら、不当請求を正式に退けることができ安心ですし、場合によっては精神的苦痛を伴ったとして、こちらが会社に対して慰謝料を請求することも可能です。
退職代行その後の法的トラブルを避けるための注意点
退職代行を利用したその後に発生するトラブルの多くは「証拠不足」や「対応不足」、「雇用契約書の記載内容」が原因です。退職代行を利用する前に有給残日数や残業代の記録、雇用契約書のコピーを手元に控えておき、会社側とやりとりしたメールの保管などをしておくと、法的トラブルを回避しやすくなります。
民間代行業者と弁護士法人の退職代行のその後の対応の違い

退職代行の「その後」を考えたとき、民間業者と弁護士法人の対応には大きな差があります。料金だけで選んでしまうと、後々トラブル対応で困るケースが少なくありません。ここでは両者の違いを整理します。
民間退職代行業者利用後のトラブル対応限界
民間業者は「退職の意思を伝える」ことしかできません。そのため、退職後に会社から損害賠償を請求されたり、有給休暇を拒否された場合には対応できず、利用者が自力で弁護士に相談する必要があります。また、退職代行完了後に発生するトラブルは、往々にして法的対応が求められます。民間業者では法律を翳した交渉ができないため、多くの業者は退職日を迎えると同時に契約が終了します。
弁護士法人の退職代行ならその後の法的問題も解決可能
弁護士法人が行う退職代行なら、未払い残業代や退職金、有給休暇の交渉も可能です。さらに、会社が不当な請求をしてきた場合も法的に反論できるため安心です。退職代行に注力している弁護士法人であれば、アフターサポートの期間も長めに設定されているので、数か月後に会社が突然不当な請求をしてきたとしても安心できます。
退職代行のその後が気になるなら弁護士法人みやびに問い合わせを

退職代行を利用したその後には、貸与品返却や書類提出、会社からの嫌がらせや損害賠償請求といったトラブルなど、多くの課題が残ります。民間業者に依頼した場合は「退職できた」だけで終わり、その後の対応はすべて自力で行わなければならないケースも珍しくありません。その点、弁護士法人みやびなら退職の成立から残業代・退職金の請求、万一の損害賠償への対応までトータルで任せられるため、安心して次のキャリアへ進むことができます。
弁護士法人みやびの退職代行サービスの特徴
弁護士法人みやびは、労働問題に強い弁護士が直接対応する退職代行サービスを提供しています。最大の特徴は、退職その後に発生する可能性のある法的トラブルまで一貫して対応できる点です。LINEを利用した無料相談も可能で、「本当に退職できるのか」「有給休暇は使えるのか」といった疑問に事前に答えることが可能です。これまで数多くの退職代行実績を持ち、依頼者の安心を第一に考えたサポートを行っているため、トラブルを避けたい人に最適な選択肢といえるでしょう。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。
退職代行のその後に関するよくある質問
退職代行を利用した後は「退職できて終わり」と考えがちですが、実際にはその後にもさまざまな課題やトラブルが発生する可能性があります。ここでは、退職代行のその後に関して多く寄せられる質問と回答をまとめました。
Q1. 退職代行を利用した後、会社から直接連絡が来ることはありますか?
A. 民間業者の場合は会社が本人に直接連絡してくることもあります。弁護士対応なら代理人を通じてしか会社は連絡できないため安心です。
Q2. 退職代行利用後に必ず返却しなければならないものは何ですか?
A. 社員証、制服、PC、スマホ、セキュリティカードなど貸与品は必ず返却が必要です。書留や宅配便など記録が残る方法を選びましょう。
Q3. 退職代行利用後に退職届は提出しなければいけませんか?
A. 会社から求められる場合があります。郵送で提出すれば問題ありません。理由は「一身上の都合」とするのが一般的です。
Q4. 退職代行を使ったことは転職活動に不利になりますか?
A. 基本的に不利になることはありません。面接では「家庭の事情」「体調不良」など前向きかつ無難な理由に置き換えるのがおすすめです。
Q5. 退職代行を使ったその後に損害賠償を請求されることはありますか?
A. 研修費用や欠員による損害を理由に請求されることがありますが、裁判で認められるケースは稀です。弁護士対応なら不当請求は退けられます。
Q6. 退職代行後に必要な書類はどのように確認すればよいですか?
A. 離職票、源泉徴収票、雇用保険被保険者証などが送られてきているか確認しましょう。届かない場合は労働基準監督署やハローワークに相談を。
Q7. 民間退職代行と弁護士法人の違いはその後に影響しますか?
A. はい。民間業者は退職完了までが範囲で、その後のトラブルには対応できません。弁護士法人なら残業代請求や不当な損害賠償への対応も可能です。