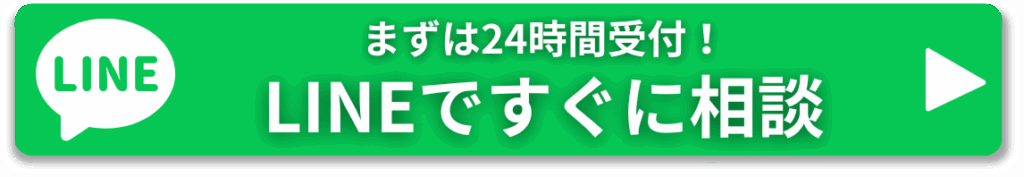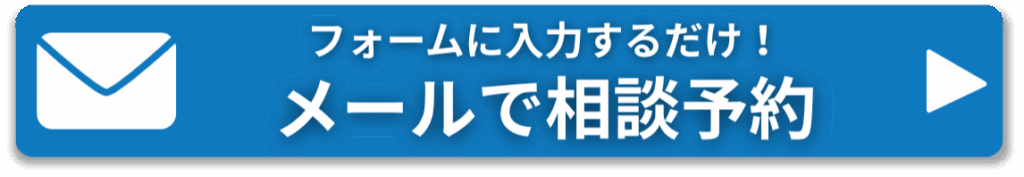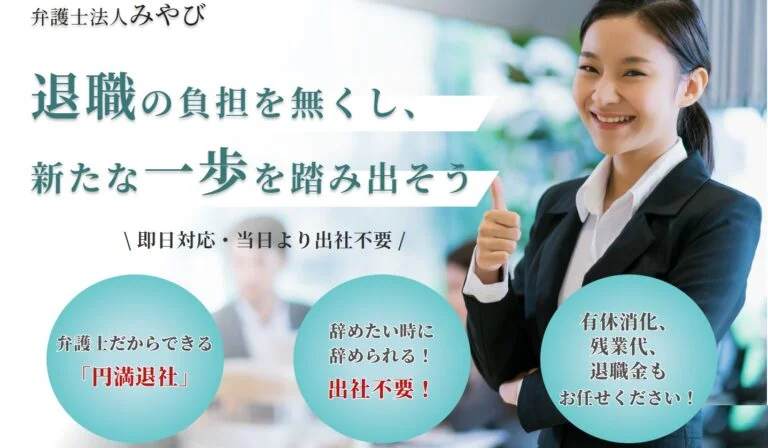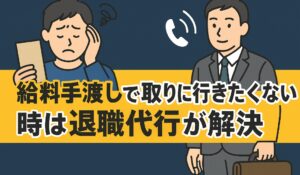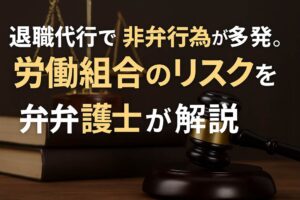退職代行の弁護士法違反と非弁行為トラブル。【弁護士解説】
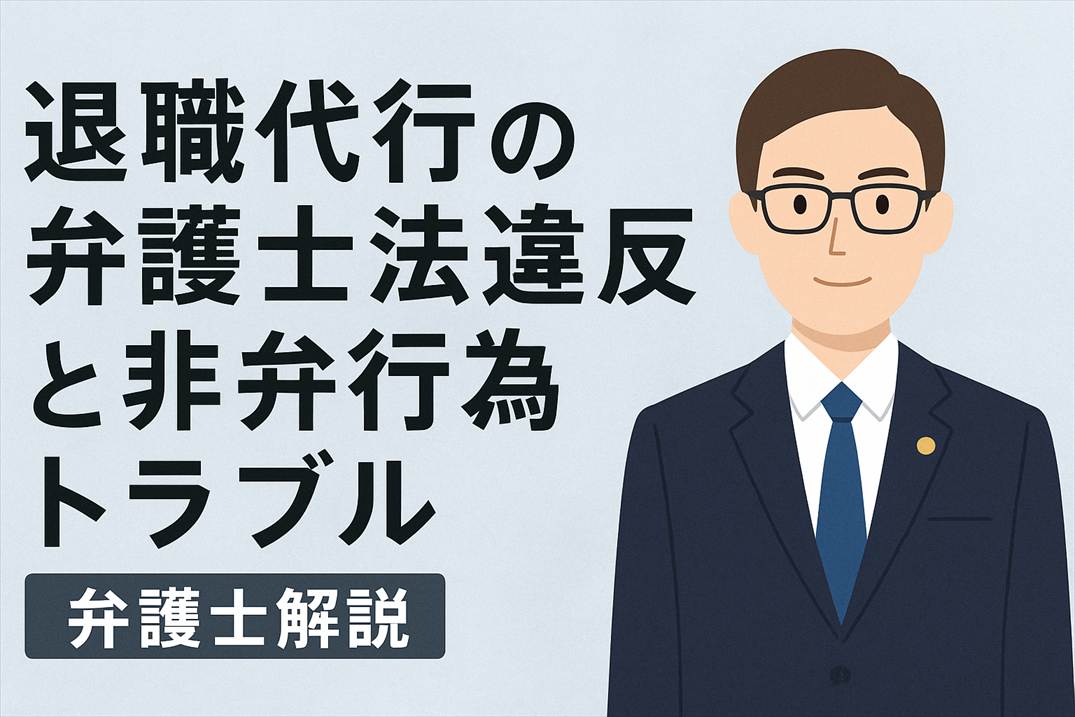
退職代行の利用者が増える一方で、「違法では?」「弁護士法に違反しているのでは?」という不安を抱く人も少なくありません。実際、近年は弁護士法第72条で禁止される「非弁行為(ひべんこうい)」に該当する退職代行が摘発されるケースもあります。
依頼している途中に代行業者が摘発されてしまった場合、業務が途中で終了してしまい、依頼者は多大な迷惑を被ります。そうならないよう、弊所弁護士法人みやびでは、弁護士による退職代行の利用を推奨しています。
【弁護士が徹底解説】退職代行の弁護士法違反・非弁行為の基礎知識

退職代行サービスを選ぶ際に最も注意すべきなのが、「弁護士法違反」や「非弁行為」に該当するリスクです。退職代行は、会社との交渉や書面対応を第三者が行うため、運営主体によっては法律上の制限を受けます。ここでは、弁護士法における禁止行為の定義と、退職代行で違法とされる具体的なケースを整理します。
弁護士法第72条で禁止される非弁行為の定義
弁護士法第72条では、弁護士資格を持たない者が「報酬を得る目的で法律事件に関する業務を行う」ことを禁止しています。退職代行の場合、会社への退職通知は誰でも行えますが、「交渉」や「請求」「法的書面の作成」は弁護士しか行うことができません。したがって、一般企業や個人が報酬を得て会社との交渉を行うと、非弁行為として処罰の対象となる可能性があります。
退職代行で違法となる具体的な行為と注意点
退職代行業者が次のような行為を行った場合、弁護士法違反となるおそれがあります。
①会社に退職日の変更や有給休暇の取得を交渉する
②未払い残業代や退職金の支払いを求める
③損害賠償請求に関する調整を行う。
これらは「法的利益に関する交渉」であり、弁護士資格がない者が行うと違法です。利用者としては、依頼前に業者がどこまで対応できるのかを必ず確認する必要があります。また、広義では退職日を調整する交渉自体も金銭が絡むため、弁護士法違反と解釈される可能性があります。
自分でできる退職代行の合法性チェックリスト
退職代行を選ぶ前に、以下のポイントを確認してみましょう。
・運営元は「弁護士法人」または「労働組合」になっているか
・公式サイトに代表者名・住所・所属弁護士会が明記されているか
・「交渉します」「会社とやり取りします」と記載されていないか
・料金体系が明確で、追加費用がないか
・契約前に書面でサービス範囲を説明しているか
これらを満たしていれば、非弁行為リスクを避け、安全な退職代行を選ぶ目安となります。
退職代行モームリ事件に見る非弁行為の実態と法的影響
2025年に報道された「退職代行モームリ」の家宅捜索事件は、退職代行業界の法的リスクを社会に広く知らしめる出来事となりました。報道によれば、同社は弁護士に依頼者をあっせんして、報酬を得ていたとのこと。これが弁護士法違反となり家宅捜索を受けました。
また、関係者の話によると、警察は退職代行の民間業者の違法性(非弁行為)も視野に、今後捜索を拡大する可能性があると指摘しています。
モームリが家宅捜索を受けた理由と経緯
SNS広告などで「弁護士が監修」「安心の退職代行」などとアピールしている退職代行モームリは、2025年10月22日、警視庁が家宅捜索をしました。理由は弁護士を依頼者にあっせんし、弁護士から報酬を得ていたためです。これは弁護士法違反となります。
弁護士あっせんで報酬を得る行為が違法とされる根拠
弁護士法では、弁護士以外の者が「法律事件の紹介やあっせん」を行い、報酬を受け取ることも非弁行為とみなされます。モームリ事件では、利用者を弁護士に紹介し、その見返りとして報酬を受け取っていた疑いが指摘されました。つまり、直接交渉を行わなくても「法律事務への関与」で報酬を得る構造自体が違法となる可能性があるのです。この点を誤解している業者も多く、注意が必要です。
「弁護士提携」をうたう退職代行サービスの危険性
「弁護士提携」「顧問弁護士監修」といった表現を用いる退職代行は一見安全に見えますが、実際には弁護士が案件に直接関与していないのが普通です。監修のみで日常業務を民間スタッフが行っている場合、法的交渉を行えば弁護士法違反となります。また、モームリのように、何かあった際に依頼者に提携先の弁護士を紹介する場合も、金銭を享受している場合は弁護士法違反となります。
この事件が退職代行業界に与えた影響と教訓
モームリ事件をきっかけに、退職代行業界では「民間業者に依頼するリスク」、「弁護士に依頼する重要性」がより明確になりました。今回のように警察から家宅捜索を受け業務の続行が難しくなると、現在依頼中の案件もストップしてしまい、依頼者は右往左往することになってしまいます。「料金が安いから」、「SNSで注目されているから」というだけで判断してしまうと、大きなトラブルに発展することになりかねません。
「会社から非弁行為だと言われた」実際のトラブル事例

退職代行を利用した際に、会社側から「その業者は非弁行為だ」「違法な退職代行だから対応できない」と指摘されるケースがあります。多くは、弁護士資格を持たない業者が会社との交渉を行っていることが原因です。
ここでは、実際に起きたトラブル事例をもとに、非弁行為が疑われた場合のリスクと、弁護士による適切な対応について解説します。
ケース1:退職代行業者の交渉を会社が拒否し退職できなかった例
ある利用者は、一般企業が運営する退職代行を通じて会社に退職意思を伝えました。しかし、業者が「有給消化を交渉」しようとしたため、会社側が「弁護士でない者が交渉するのは違法」として連絡を拒否。結果的に、退職手続きが進まず、本人が改めて弁護士を通じて通知をやり直す必要がありました。非弁行為の疑いをかけられると、退職が遅延するリスクがあります。
ケース2:未払い残業代請求で弁護士法違反を指摘されたケース
別の事例では、退職代行業者が会社に対して未払い残業代の支払いを求めたことで、弁護士法第72条に抵触する疑いが生じました。会社の顧問弁護士が「違法な請求である」と主張し、交渉自体を拒否した結果、利用者が望む結果を得られませんでした。金銭請求や契約内容の交渉を行う場合は、弁護士のみに認められた法的代理行為であることを理解しておく必要があります。
ケース3:本人確認不足で退職届が無効とされたケース
非弁行為とは別の問題として、退職代行業者が本人確認を十分に行わず、会社が「退職の意思を確認できない」として退職届を無効とした例もあります。会社側が「本人の意思ではない」と判断すると、退職の効力が発生しないおそれがあります。弁護士対応の退職代行では、正式な委任契約に基づき、法的に有効な通知を行うため、このようなトラブルは発生しません。
違法な退職代行を利用した際に発生する深刻なトラブル

弁護士資格のない退職代行業者に依頼した場合、法的に無効な手続きとなり、思わぬトラブルに発展することがあります。非弁行為に該当する行為を業者が行うと、会社側が手続きを拒否する、あるいは退職が無効となるおそれもあります。ここでは、実際に起こり得る主なリスクを整理し、違法な退職代行を避けるべき理由を具体的に解説します。
退職無効リスクと法的地位の残存
非弁行為に該当する退職代行が行った通知は、法的には効力を持たない場合があります。つまり、利用者が退職したつもりでも、会社側では「在職扱い」のままになってしまうリスクがあるのです。この状態が続くと、給与計算や社会保険、雇用保険の処理が適切に行われず、後日トラブルにつながることがあります。弁護士対応であれば、法的に有効な退職通知を代理送付できるため、確実に退職が成立します。
損害賠償請求・返金トラブルの実例
違法な退職代行を利用した結果、会社側から「業務に支障が出た」として損害賠償を請求されるケースも報告されています。さらに、退職できなかったにもかかわらず「返金対応を拒否された」「連絡が取れなくなった」といった事例も存在します。非弁業者の場合、法的責任を負えないため、利用者が泣き寝入りする形になることが多いのが現実です。
有給・退職金・未払い賃金が請求できなくなるケース
退職に伴う有給休暇の消化や退職金、未払い残業代などの請求は、弁護士でなければ交渉できません。非弁行為に該当する業者では、こうした請求を行う権限がないため、結果的に利用者が本来受け取れるべき金銭を失うリスクがあります。弁護士対応の退職代行であれば、退職手続きと同時に法的請求まで含めて一括で進められます。
退職代行の運営主体別:弁護士法違反リスク比較

退職代行サービスと一口に言っても、その運営主体には「一般企業(民間業者)」「労働組合」「弁護士法人」の3つのタイプがあります。この運営形態の違いによって、法的にできること・できないこと、そして弁護士法違反のリスクが大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴と注意点を比較しながら、どのタイプの退職代行が安全で信頼できるのかを解説します。
一般企業型→非弁行為で違法性が高い
一般企業が運営する退職代行サービスは、最もトラブルが多く、弁護士法第72条に抵触する可能性が極めて高いとされています。弁護士資格を持たないスタッフが、会社とのやり取りや有給交渉を行うこと自体が「非弁行為」に該当します。形式的には「本人の意思を伝えるだけ」としていても、実質的な交渉を行えば違法です。こうした業者は、会社からの連絡拒否や損害賠償請求を招くリスクが高く、避けるべきといえます。
労働組合型→団体交渉権はあるが法的限界あり
労働組合が運営する退職代行は、団体交渉権を持つため、勤務条件や退職日の調整について会社と話し合うことが可能です。ただし、あくまで「労働条件の改善」や「団体交渉」に限定され、個別の金銭請求(未払い賃金や損害賠償など)には対応できません。また、退職証明書や離職票の発行など、法律手続き上の問題が発生した場合は弁護士の介入が必要です。法的限界を理解したうえで利用を検討する必要があります。
弁護士法人型→唯一すべての交渉と請求が可能
弁護士または弁護士法人が運営する退職代行は、法的代理権を持つ唯一の存在です。退職の意思表示はもちろん、有給休暇の取得交渉、未払い残業代や退職金の請求まで、すべてを合法的に行うことができます。会社からの損害賠償請求にも代理人として対応できるため、依頼者は一切の連絡・交渉を行う必要がありません。安心・確実・合法という三拍子がそろうのが、弁護士対応の退職代行の最大の強みです。
会社が「違法だ」と主張してきた場合の弁護士による法的対処法

退職代行を利用した際、会社側が「その退職は違法だ」「非弁行為ではないか」と主張してくるケースがあります。特に、弁護士以外の業者が関与している場合、会社が法的無効を理由に退職を認めないトラブルが発生することもあります。ここでは、会社が違法性を主張してきた場合に、弁護士がどのように対応し、依頼者の権利を守るのかを具体的に解説します。
弁護士が代理人なら会社の主張は法的に無効となる理由
弁護士が依頼者の代理人として正式に受任している場合、退職の意思表示は法的に有効です。会社が「違法だ」と主張しても、弁護士法第72条に基づく正式な代理権があるため、手続きが無効とされることはありません。弁護士は退職通知書や内容証明郵便などの書面を通じて、退職意思を明確に伝えるため、証拠としても十分に機能します。
退職の自由は民法627条・労働基準法で絶対保障されている
日本の法律では、労働者には「退職の自由」が明確に保障されています。民法627条により、労働契約は労働者の意思で解除できると定められています。さらに、労働基準法でも強制労働は禁止されており、会社が退職を拒否すること自体が違法行為にあたります。弁護士はこれらの法的根拠をもとに、会社の不当な主張を退けることができます。
本人確認要求への適切な対応方法
退職代行を通じて退職を申し出た際、会社が「本人確認が取れない」として手続きを拒むケースもあります。弁護士が代理人として受任していれば、委任契約書・受任通知・弁護士登録番号の提示によって、本人確認が法的に完結します。これにより、会社は「本人確認ができない」という理由で手続きを遅らせることはできません。
弁護士対応の退職代行が安全な理由【弁護士法人みやび】

退職代行サービスの中には、弁護士法違反や非弁行為に該当するリスクを抱える業者も存在します。その中で、弁護士が直接対応する退職代行は、唯一すべての手続きを合法的に行える安全な方法です。
ここでは、弁護士法人みやびが提供する退職代行サービスが、どのように法的リスクを回避し、依頼者を守る仕組みを持っているのかを解説します。
弁護士だけが持つ「代理交渉権」と法的保護
弁護士は弁護士法に基づき、依頼者の代理人として会社との交渉・通知・請求を行うことが認められています。これは、一般企業や労働組合にはない「独占的権限」です。退職の意思表示はもちろん、有給休暇の取得交渉、残業代請求、退職金の支払い要求まで、すべてを法的に進めることが可能です。弁護士法人みやびでは、依頼を受けた弁護士がすべてのやり取りを直接担当し、非弁行為のリスクを完全に排除しています。
退職日・有給・未払い請求を一括で対応可能
弁護士法人みやびの退職代行では、退職手続きだけでなく、有給休暇の消化や未払い賃金の請求まで一括で対応可能です。これにより、利用者は追加で他の機関や業者に依頼する必要がなく、退職に関するすべての問題を一度の依頼で解決できます。また、会社が退職日を不当に遅らせたり、給与を支払わなかった場合でも、弁護士が法的手段を通じて迅速に対応します。
会社も拒否できない法的根拠と安心サポート
弁護士が代理人として退職通知を送付した場合、会社はそれを拒否することはできません。退職の意思表示は民法627条で保障されており、弁護士を介して行われた通知は法的に有効です。弁護士法人みやびでは、内容証明郵便などの確実な手段で通知を行うため、会社が「知らなかった」「受け取っていない」と主張する余地もありません。法的根拠に基づく確実な退職をサポートします。
他社で断られた案件も解決した実績紹介
弁護士法人みやびには、他の退職代行業者で対応できなかった複雑なケース(損害賠償請求・懲戒処分・社宅トラブルなど)を解決してきた豊富な実績があります。特に、法的判断が求められるケースでは、弁護士による直接対応が不可欠です。過去には、退職拒否を受けた会社と交渉の末、即日退職を実現した事例もあります。こうした経験に基づくノウハウが、依頼者の安心と確実な解決につながっています。
【まとめ】退職代行トラブルを防ぐなら弁護士法人みやびへ

退職代行サービスは正しく選べば安全で有効な手段ですが、非弁行為や弁護士法違反に該当する業者を選んでしまうと、退職そのものが無効になるリスクもあります。信頼できる弁護士による対応こそが、確実かつ安心して退職を進めるための唯一の方法です。
弁護士法人みやびならLINE相談&退職完了後も無期限サポート
弁護士法人みやびでは、退職代行の依頼をEmail・LINE・電話で無料で受け付けています。契約する前に理想の退職の実現の有無や各種請求の可否などを質問できるので、ギャップがありません。
また、実際の退職交渉では弊所の経験豊富な弁護士が直接対応し、退職日や有給、未払い賃金請求なども含めて法的に適切な方法で退職をサポートします。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。
退職代行の弁護士法違反・非弁行為に関するよくある質問
退職代行サービスの中には、弁護士法に抵触するおそれがあるものも存在します。「非弁行為」と呼ばれる行為は法律で禁止されており、知らずに利用するとトラブルに巻き込まれる可能性があります。ここでは、退職代行を利用する前に知っておきたい弁護士法違反・非弁行為の基礎知識を、弁護士法人みやびが分かりやすく解説します。
質問1.退職代行を利用すると弁護士法違反になることはありますか?
退職の意思を伝えるだけなら違法ではありませんが、弁護士資格のない業者が会社と交渉したり、未払い金の請求を行うと弁護士法第72条に違反するおそれがあります。特に「退職日を調整します」「有給取得を交渉します」といったサービス内容を掲げている場合、非弁行為に該当する可能性が高いといえます。
質問2.「非弁行為」とは具体的にどんな行為を指しますか?
非弁行為とは、弁護士資格を持たない者が報酬を得て法律事件に関する業務を行う行為です。退職代行の場合、退職金・未払い残業代・損害賠償などの請求を代わりに行うこと、また会社と退職条件を交渉することが該当します。これらの業務は弁護士のみが認められた法的代理行為です。
質問3.退職代行モームリ事件はなぜ弁護士法違反とされたのですか?
退職代行モームリは、利用者を弁護士にあっせんし、その報酬を受け取っていた疑いがありました。弁護士以外の者が法律事務を紹介・仲介して報酬を得ることも、弁護士法で禁止されている「非弁行為」です。この事件は退職代行業界全体に大きな影響を与え、法令遵守の重要性が改めて認識されるきっかけとなりました。
質問4.「弁護士監修」と「弁護士対応」はどう違うのですか?
「弁護士監修」は、弁護士がサービス内容を提携先にアドバイスしただけで、実際の退職交渉は一般スタッフが行います。一方で「弁護士対応」は、弁護士が依頼者の代理人として会社と直接交渉するものです。非弁行為を避け、法的に確実な手続きを行うには、弁護士対応型の退職代行を選ぶことが不可欠です。
質問5.弁護士法人みやびの退職代行は他社と何が違いますか?
弁護士法人みやびでは、すべての案件を弁護士が直接担当します。退職通知・有給消化・未払い請求などの交渉を合法的に行うことができ、非弁行為リスクを完全に排除しています。LINE・メールでの無料相談にも対応しており、初めての方でも安心して利用できます。
質問6.会社が「違法な退職代行だ」と言ってきた場合はどうすればいいですか?
弁護士が正式に代理人として受任している場合、退職の意思表示は法的に有効です。民法627条および労働基準法により、労働者には退職の自由が保障されています。会社が「違法」と主張しても、弁護士対応の退職代行であればその主張は法的に通用しません。