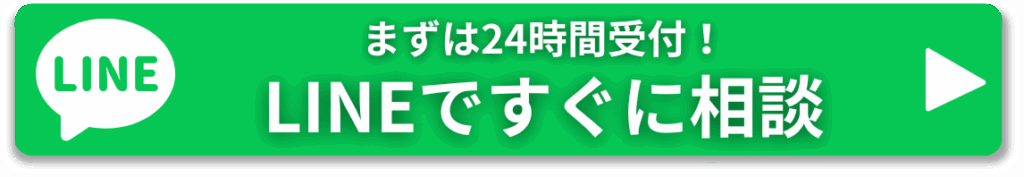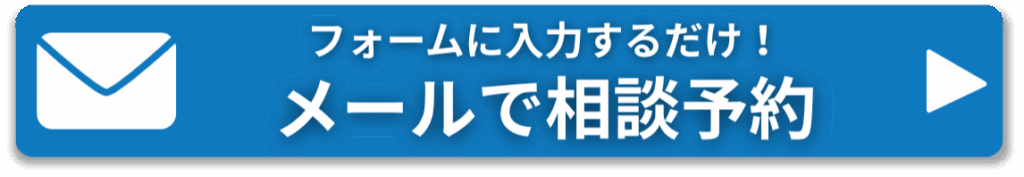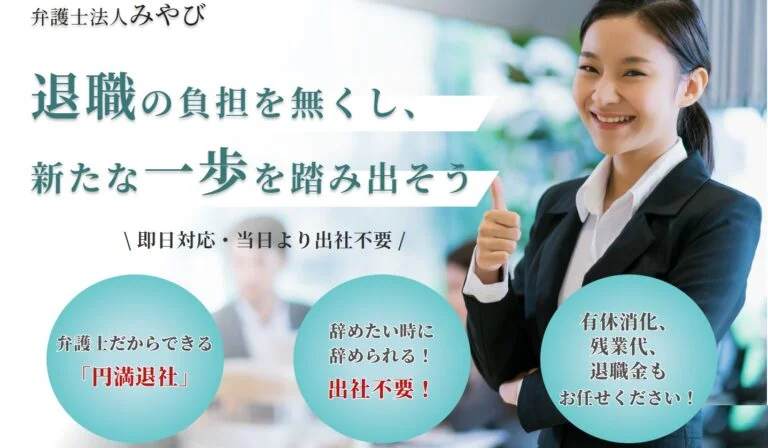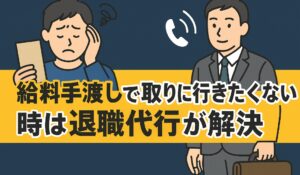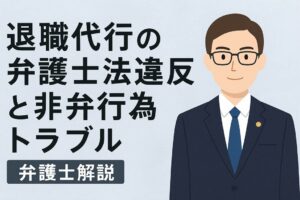退職代行で非弁行為が多発。労働組合のリスクを弁護士が解説
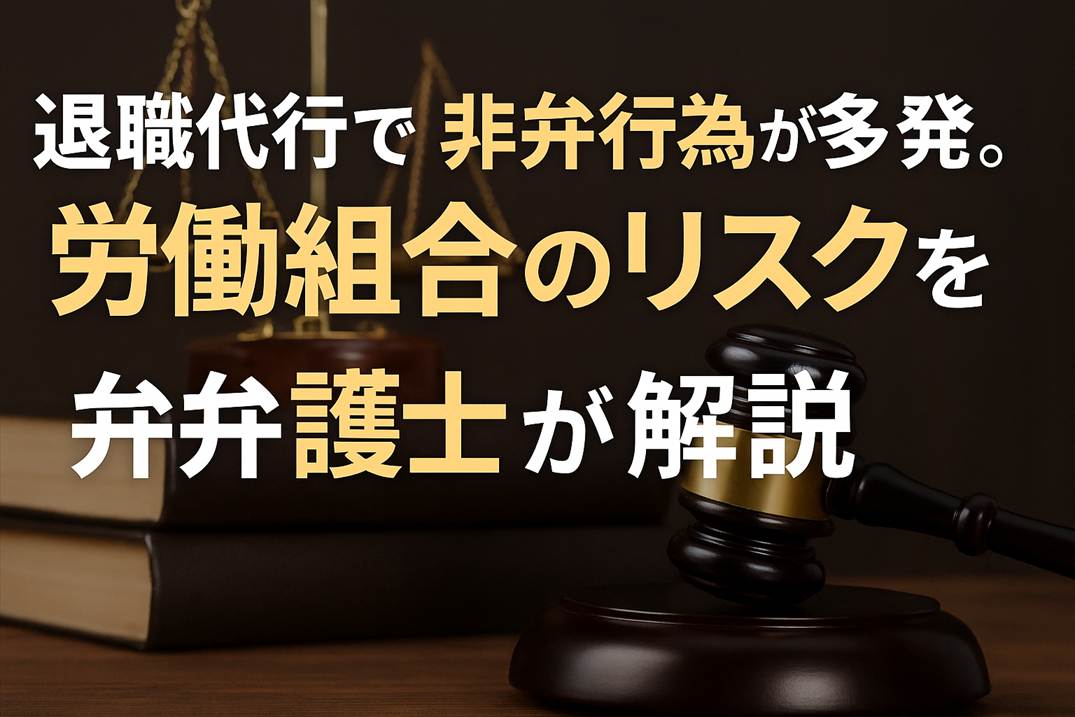
退職代行サービスは、今や一般的な選択肢となりつつあります。しかし、その一方で「非弁行為(ひべんこうい)」に該当する違法なサービスが増加しているのも事実です。特に「労働組合提携」「ユニオン型」などを名乗る退職代行の中には、法的根拠を誤解した運営が行われ、利用者がトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
この記事では、弁護士法72条に基づく「非弁行為」の定義から、労働組合が退職代行を行う際の法的限界、そして安全な退職代行サービスの選び方までを弁護士が詳しく解説します。退職を検討している方はもちろん、すでに退職代行の利用を考えている方も、ぜひ参考にしてください。
退職代行における「非弁行為」とは?弁護士法違反の判断基準を解説

まず理解しておきたいのは、退職代行サービスにおける「非弁行為(ひべんこうい)」がどのような行為を指すのかという点です。表面的には「退職の意思を伝えるだけ」のように見えても、法律上は弁護士しか行えない「法律事務」に該当する行為が含まれているケースがあります。ここでは、非弁行為の定義と判断基準を詳しく見ていきましょう。
弁護士法第72条における「非弁行為」の定義
弁護士法第72条では、「弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関する業務を行ってはならない」と定められています。つまり、弁護士資格を持たない個人や団体が、報酬を受け取って法律事務(交渉・請求・和解など)を行うと、非弁行為に該当します。退職代行サービスにおいても、会社との交渉や金銭請求を行えば、この条文に違反するおそれがあります。
「法律事務」に該当する行為とは?退職代行に当てはまる範囲
法律事務とは、単なる伝達や事務連絡を超えて、「相手方との交渉」「条件調整」「権利の主張」などを含む行為を指します。例えば「退職日を調整する」「未払い残業代を請求する」「会社に有給消化を認めさせる」などはすべて法律事務に該当します。これらを弁護士資格のない業者が行えば、非弁行為として処罰対象になる可能性があります。
退職代行で違法とされる典型的な非弁行為の例
実際に問題視されている非弁行為の多くは、業者が利用者に代わって会社と交渉するケースです。たとえば「会社と交渉して退職日を早める」「有給を使えるように話をまとめる」といった行為は、弁護士でない限り行えません。また、退職後に会社が「退職日が無効だ」「引継ぎが完了していない」と主張した場合、非弁行為によるトラブルとして訴訟に発展することもあります。
非弁行為が刑事罰の対象となる理由と罰則内容
非弁行為は、弁護士法第77条により刑事罰の対象となります。罰則は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」と重く、過去には実際に摘発された退職代行業者も存在します。利用者自身は処罰されないものの、違法業者に依頼すると退職手続きが無効になったり、会社との紛争に巻き込まれたりする危険性があります。安全に退職を進めるためには、必ず弁護士が直接対応する退職代行を選ぶことが重要です。
労働組合の退職代行が「合法」となる条件と限界|団体交渉権の正しい理解

「弁護士以外が退職代行を行うのは違法では?」という疑問に対し、よく挙げられるのが「労働組合であれば合法」という主張です。確かに、労働組合には法律で認められた団体交渉権があり、一定の範囲内で退職に関する交渉を行うことが可能です。ただし、その範囲を超えてしまうと、たとえ労働組合でも非弁行為に該当するおそれがあります。ここでは、労働組合型退職代行が合法とされる理由と、その限界を明確に解説します。
憲法28条と労働組合法が保障する「団体交渉権」
日本国憲法第28条は、「勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権」を基本的人権として保障しています。これに基づいて制定された労働組合法では、労働者が労働条件の改善などを目的として団結し、使用者(会社)と交渉する権利を認めています。つまり、労働組合が退職交渉を行うこと自体は、労働組合法により一定の範囲で許容されているのです。
労働組合が退職交渉で行える範囲
労働組合が合法的に行えるのは、団体交渉の範囲内にある「労働条件や待遇」に関する交渉です。退職代行においては、主に「退職の意思を伝える」「退職日や有給休暇の取得を確認・交渉する」「会社からの不当な引き止めを防ぐ」といった行為が該当します。
さらに、労働組合は団体交渉権に基づき、「未払い残業代や未払い賃金の請求」など、労働条件に関する金銭請求を伴う交渉も合法的に行うことができます。
一方で、慰謝料などの損害賠償請求や、訴訟・労働審判といった法的な手続きの代理など、労働条件の交渉の範囲を超え、法律的な紛争解決を目的とする行為は、法律上は弁護士でなければ行えません。
【要注意】労働組合型退職代行で多発する非弁行為の典型パターン

「労働組合だから安心」と思って依頼した退職代行が、実は非弁行為だった。このようなトラブルが近年増加しています。労働組合を名乗る団体の中には、法的に届出がなかったり、実態のない組織であったりするケースも少なくありません。ここでは、弁護士が実際に相談を受けた事例をもとに、労働組合型退職代行に多い違法・不適切なケースを紹介します。
届出のない「ペーパー組合」や「幽霊組合」による代行業務の実態
最も多いのが、実際には労働委員会への届出を行っていない「ペーパー組合」が退職代行を名乗るケースです。これらの組織は団体交渉権を持たないため、本来は交渉や請求を行う資格がありません。それにもかかわらず「労働組合だから合法」と宣伝して依頼を集める事例が後を絶ちません。結果として、依頼者が退職後に会社から「手続きが無効」と指摘されるケースもあります。
民間業者が労働組合の名義を借りる“名義貸し型”違法スキーム
もう一つの典型例が、実際の運営を民間企業が行い、形式上だけ労働組合名を使う「名義貸し型」スキームです。この場合、代行の実務担当者は組合員ではなく、ただの業者スタッフであることがほとんどです。実態としては民間業者による退職代行であり、会社と退職条件を交渉すれば非弁行為に該当します。こうした業者は摘発対象となる可能性もあり、依頼者自身がトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
報酬目的で交渉を行う場合の違法性と摘発事例
労働組合であっても、報酬を得る目的で個人の退職交渉を行えば、弁護士法第72条に違反します。実際に過去には、組合名義で退職代行を行い、会社との交渉を有料で請け負った業者が非弁行為として摘発されています。団体交渉は労働条件の改善を目的としたものであり、個人退職をビジネス化した場合には違法性が強くなる点に注意が必要です。
利用者が被害に遭いやすい「労働組合を装った詐欺的サービス」
一部では、実際には組合員登録も行わず、「加入不要」「誰でもすぐに依頼OK」といった広告を出しているサービスもあります。こうした業者は、形式上「労働組合型」と名乗りながら、内部では通常の民間退職代行と変わらない運営をしていることが多く、非弁行為に該当するリスクが非常に高いです。
「提携」「監修」を謳う退職代行サービスの落とし穴と違法性の判断基準

近年、「弁護士監修」「労働組合提携」などと表記した退職代行サービスが急増しています。一見すると法的に安心できそうな印象を与えますが、実際には弁護士や労働組合が業務に関与していないケースも多く、非弁行為に該当するおそれがあります。ここでは、提携・監修・顧問などの表現に潜むリスクと、違法性を見抜く判断基準を解説します。
「労働組合提携」や「監修」=合法ではない理由
「労働組合提携」「弁護士監修」と記載していても、その団体や弁護士が実際に退職代行業務を行っていない場合、法的には何の効力もありません。単に名前を貸しているだけの“形式的な提携”であれば、実質的には民間業者が退職代行を行っているのと同じです。弁護士法72条に抵触する非弁行為に該当する可能性が高く、利用者が知らずに違法行為に関与してしまうリスクがあります。
弁護士監修の限界と、誤認・責任回避リスク
弁護士が監修しているという表現も注意が必要です。「監修」はあくまでマニュアルや書面のチェックレベルにとどまることが多く、実際の退職交渉や法的手続きを弁護士が行っているわけではありません。そのため、万が一トラブルが発生しても、監修弁護士が責任を負うことはありません。利用者が「弁護士が関与しているから安全」と誤認するような表現は、景品表示法や特定商取引法の観点からも問題となる場合があります。
非弁行為を見抜くためのチェックリスト4項目
退職代行サービスを選ぶ際は、以下の4つのポイントを確認することで非弁行為の可能性を見極めることができます。
- 実際に対応する担当者が「弁護士」または「労働組合員」であるか
- 弁護士や労働組合が、契約書や通知書に正式な署名・押印をしているか
- 「監修」「提携」「顧問」などの表現に実態があるか(契約内容を開示できるか)
- 料金体系に「交渉」や「請求」などの文言が含まれていないか
上記のうち1つでも不明確な点があれば、非弁行為である可能性があります。特に「弁護士監修」「労働組合提携」という文言のみを強調しているサイトには注意が必要です。法的リスクを回避するには、実際に弁護士が直接対応する退職代行を選ぶことが最も安全です。
合同労組・ユニオンの退職代行で起こりがちなトラブルと法的リスク

「ユニオン(合同労組)だから安全」と考えて退職代行を依頼したものの、後になってトラブルに発展するケースは少なくありません。合同労組は複数の企業に勤める労働者で構成されるため、活動範囲が広い一方で、運営実態が不透明な団体も存在します。ここでは、合同労組やユニオンによる退職代行で実際に起きている問題点と法的リスクを整理して解説します。
合同労組とは?複数企業を対象に活動する仕組み
合同労組(ユニオン)とは、同一企業に限らず、さまざまな業種・企業の労働者が加入できる労働組合のことです。職場内に組合がない個人労働者でも加入できるため、労働者の権利を守るために重要な存在です。退職代行サービスの一部は、この合同労組と提携して業務を行っていると称しています。しかし、すべての合同労組が法的に適切な活動をしているわけではなく、届出を怠っていたり、実際には活動実績がない「名ばかりユニオン」も見られます。
ユニオン名義を悪用した違法代行の実例
過去には、実態のない合同労組が名義を貸して民間業者に退職代行を行わせていた事例があり、非弁行為として警察に摘発されたケースもあります。このような業者では、依頼料だけを受け取って連絡を絶つ、退職手続きを放置するなどの被害が報告されています。法的保護を受けるどころか、依頼者がトラブルの当事者となってしまうリスクがあるため注意が必要です。
ユニオンを利用する際は、その組織が正式に届出を行っているか、団体交渉の実績があるか、実際に対応する担当者が組合員であるかを必ず確認しましょう。疑わしい場合は、弁護士に直接相談してから依頼するのが安全です。
非弁行為を行う業者に依頼してしまった場合の法的リスクと被害事例
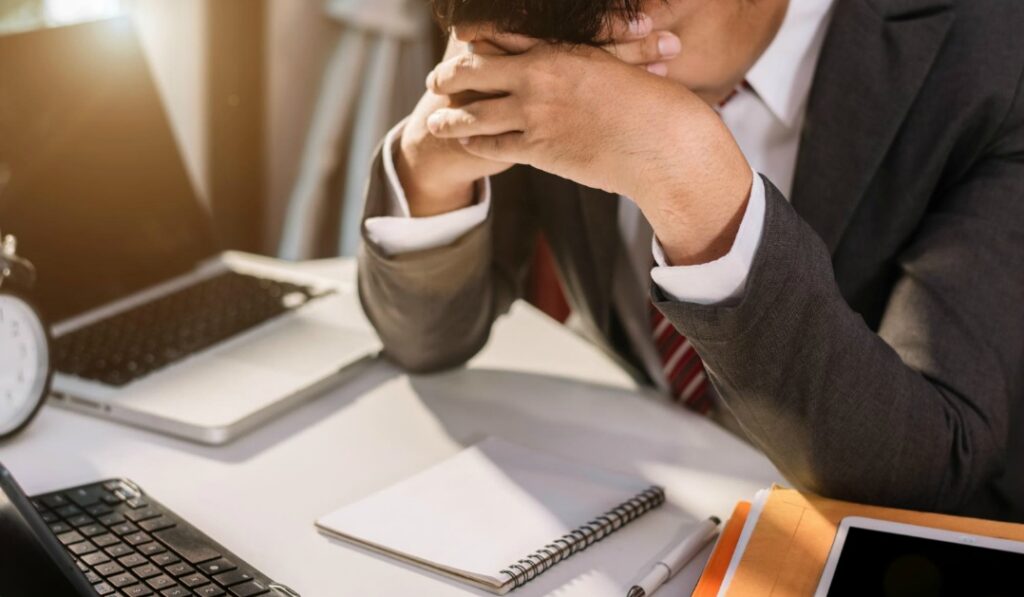
「弁護士監修と書いてあったから安心だと思った」「労働組合と提携していると説明された」といった理由で退職代行を依頼した結果、非弁行為に巻き込まれてしまうケースが増えています。非弁行為を行う業者に依頼すると、退職手続きが無効になるだけでなく、懲戒処分や損害賠償請求など、思わぬ法的トラブルに発展することがあります。ここでは、実際に起きた被害例を交えながら、主なリスクを解説します。
退職が無効になるリスクと会社からの懲戒処分の可能性
非弁業者が本人の代理として退職交渉を行った場合、会社はその交渉を「無効」と主張することができます。弁護士以外の第三者が退職日や金銭請求などを交渉した行為は、弁護士法72条に違反しており、法的効力を持ちません。その結果、退職が成立していないとみなされ、懲戒処分や解雇通知を受けるケースも報告されています。とくに無断欠勤中の依頼では、リスクがさらに高まります。
損害賠償・返金トラブルなど金銭面の被害
非弁業者に依頼した後、「退職が完了しなかった」「途中で連絡が取れなくなった」というトラブルは少なくありません。退職が成立しないまま業務が中断されたり、依頼金を返金してもらえなかったりする被害報告も多く寄せられています。また、悪質な業者では、追加料金名目で不当請求を行うケースも確認されています。これらは消費者契約法や特定商取引法にも抵触する可能性があります。
実際の被害事例:非弁行為でトラブルとなったケース
- 事例1:「労働組合提携」を名乗る民間業者に依頼したが、会社との交渉を勝手に行い非弁行為が発覚。結果、会社が交渉内容を無効とし、退職が未成立に。
- 事例2:弁護士監修と記載されたサイト経由で依頼したところ、途中で業者が音信不通に。退職が進まず、料金も返金されずに終わった。
- 事例3:格安料金の退職代行を利用したが、会社に「違法業者を使った」と指摘され、懲戒処分を受けた。その後、弁護士に再依頼してようやく退職が成立。
このように、非弁行為を行う業者に依頼した場合、金銭的・社会的な不利益を被る可能性があります。退職は人生の重要な手続きであり、安易に格安業者を選ぶことは避けるべきです。弁護士が対応する退職代行を選ぶことで、法的リスクを完全に回避し、確実に退職を成立させることができます。
非弁行為のない安全な退職を望むなら「弁護士」に依頼すべき理由

非弁行為のリスクを避け、安全かつ確実に退職を成立させたい場合、最も信頼できるのは弁護士が対応する退職代行です。弁護士には、法律に基づいて退職手続きを代理できる権限があり、依頼者の権利を守りながらすべての交渉を合法的に進めることができます。ここでは、弁護士依頼がなぜ安全なのかを具体的に見ていきましょう。
民間・労働組合・弁護士の対応範囲の違い【決定版比較表】
退職代行サービスは「弁護士」「労働組合」「民間業者」の3形態に分類されます。それぞれの対応範囲と法的リスクを整理すると、弁護士対応の優位性が明確になります。
| 運営主体 | 対応範囲 | 法的リスク | 平均費用 | 非弁行為リスク |
|---|---|---|---|---|
| 弁護士 | 退職通知・交渉・請求・法的手続きすべて可能 | なし(完全に合法) | 5〜8万円 | ゼロ |
| 労働組合 | 訴訟や賠償対応は不可 | 越権交渉で非弁行為の可能性 | 3〜8万円 | 中 |
| 民間業者 | 退職意思の伝達のみ可能 | 交渉を行うと弁護士法違反 | 2〜5万円 | 高 |
この比較表からも分かる通り、弁護士対応であれば退職に関するあらゆる行為を合法的に行うことができ、他の業者に比べて法的トラブルのリスクがありません。特に無断欠勤や会社との交渉が必要なケースでは、弁護士対応以外の選択肢は危険です。
弁護士だけが対応できる「法的な交渉・請求」の範囲と効果
弁護士は、弁護士法第72条に基づいて報酬を得て法律事務を扱うことが認められています。そのため、退職日の調整、有給休暇の取得交渉、未払い残業代の請求、退職金の支払い要求など、すべての交渉を合法的に代理できます。これらの行為は、弁護士資格を持たない業者が行えば非弁行為に該当し、刑事罰の対象となる可能性があります。
労働組合型の退職代行業者はこれらの交渉を合法で行えるものの、法の専門家が対応するわけではなく、民間の代行業者が隠れ蓑として労働組合に加盟しているだけの業者がほとんどなのが実情のため、違法性が非常に高いと言われています。
【弁護士法人みやび】非弁行為リスクゼロの安心退職代行サービス

弁護士法人みやびは、弁護士がすべての案件を直接対応する「完全弁護士対応型」の退職代行サービスです。弁護士資格を持たない民間業者や、一部の労働組合型サービスとは異なり、法律に基づいた適法な手続きで、確実かつ安全に退職を完了させます。ここでは、みやびの特徴と実績を紹介します。
料金体系と無料相談の流れ(透明性の訴求)
弁護士法人みやびの退職代行は、全国一律の明確な料金設定で、追加費用は一切かかりません。相談は無料で、LINEまたはメール、電話で依頼から契約まで受け付けています。契約後は弁護士が直接対応し、退職の通知・交渉・書面処理まで一貫して行います。
非弁行為の心配がなく、法的に確実な手続きを希望する方は、弁護士法人みやびによる「完全弁護士対応退職代行」を選ぶことで、安心して次のステップに進むことができます。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。
退職代行と非弁行為・労働組合に関するよくある質問
退職代行サービスを利用する際、「非弁行為」や「労働組合との関係」について誤解されるケースが多く見られます。弁護士が対応しているのか、労働組合がどこまで交渉できるのかを正しく理解していないと、思わぬトラブルに発展するおそれもあります。ここでは、退職代行と非弁行為・労働組合に関するよくある質問をQ&A形式で解説します。
Q1. 非弁行為とは何ですか?
非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得て法律事務(交渉・請求・和解など)を行うことを指します。退職代行サービスが会社と条件交渉や金銭請求を行うと、弁護士法第72条に違反するおそれがあります。
Q2. 労働組合の退職代行はすべて合法ですか?
いいえ。労働組合にも団体交渉権はありますが、その範囲を超えると非弁行為となります。とくに「ペーパー組合」や「名義貸し型」の業者は違法リスクが高いため注意が必要です。
Q3. 「弁護士監修」や「労働組合提携」と書かれていれば安全ですか?
必ずしも安全とは限りません。監修や提携は名義上だけの場合も多く、実際に弁護士や組合が業務を行っていないケースでは、法的効力がありません。
Q4. 非弁行為を行う業者に依頼するとどうなりますか?
退職手続きが無効になる、懲戒処分を受ける、返金トラブルに巻き込まれるなどのリスクがあります。実際に摘発された退職代行業者も存在します。
Q5. 安全な退職代行を選ぶにはどうすればいいですか?
実際に弁護士が対応しているかを確認することが最も重要です。契約書に弁護士名が明記され、法律事務所が運営しているサービスを選びましょう。弁護士法人みやびのように完全弁護士対応であれば、非弁行為の心配は一切ありません。