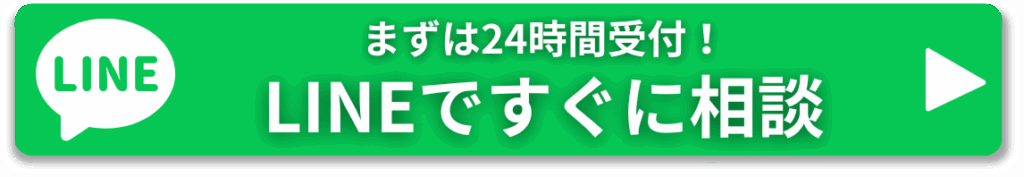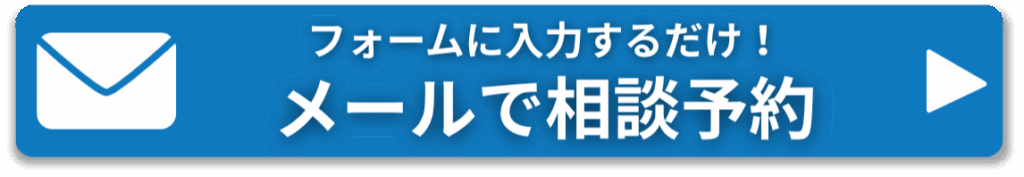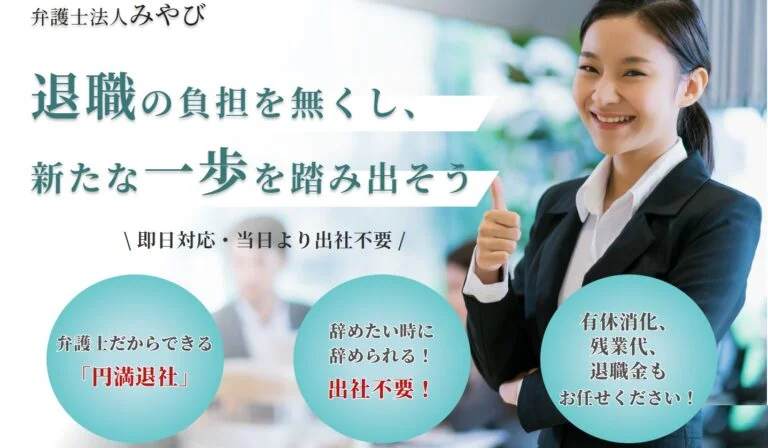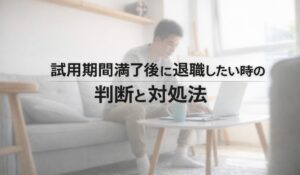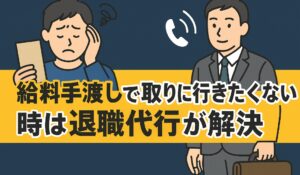退職代行で即日退職できないケースとリスクの解決策を解説

仕事を辞めたいけれど、「退職代行を利用すれば本当に即日退職できるの?」という疑問もあります。多くの民間の退職代行業者がホームページ上で即日退職をPRしていますが、実際は法律や会社の規定、業種、雇用形態によっては即日退職が難しいこともあります。
そこで、今回は退職代行を利用して即日退職を目指す際の条件や注意点、万が一即日退職ができない場合の解決策を詳しく解説します。
弊所「弁護士法人みやび」では、退職代行の手続きと交渉にあたっては弁護士が直接行いますので、即日退職できない問題を最小限に抑えることができます。まずはLINEによる無料相談窓口をご利用ください。
退職代行で即日退職できる条件とリスク・注意点

退職代行サービスを利用すれば、必ずしも誰でも即日退職できるわけではありません。実現するためには法律や労働契約のルールを満たす必要があり、同時にリスクを理解しておかなければなりません。
即日退職が可能となる条件には、次のようなケースがあります。
・有給休暇が残っている場合:残日数を消化する形で実質的に即日退職が可能
・試用期間中や契約社員の更新直前:雇用の安定性が低く、比較的退職を認められやすい
・勤務継続が困難な正当事由がある場合:心身の不調やパワハラなど、労働契約を続けられない事情があるとき
一方で、即日退職を希望する際には注意点もあります。従業員が突然辞めることで会社に損害が発生すると、引き継ぎ不足や損害賠償の請求といったトラブルにつながる可能性があります。また、退職代行業者の種類によっては対応できる範囲が限られ、特に民間業者は法律上の交渉権を持たないため、「即日退職ができない」と判断されることも少なくありません。
確実に即日退職を実現したい場合は、条件を満たしているかどうかを確認するとともに、リスクをカバーできる弁護士対応の退職代行を選ぶことが重要です。
退職代行を使わないで自力で即日退職はできないのが現実

退職届を提出すれば今日から辞められると考える人もいますが、現実には自力で即日退職を実現するのは非常に困難です。法律の制約や会社側の対応によって、退職をスムーズに進められないケースが多いためです。ここでは、自力で即日退職が難しい理由を法律面と実務面から解説します。
法律上の「2週間ルール」による制約
民法627条では、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば労働契約を解除できると定められています。つまり、会社に「今日辞めます」と伝えたとしても、法律上は即日退職は成立せず、原則として2週間後に退職日が到来します。
例外的に有給休暇を利用して2週間を消化する形を取れる場合もありますが、有給残日数がない場合は欠勤扱いになり、会社からトラブル視されることもあります。この「2週間ルール」が、自力での即日退職を不可能にしている最大の要因です。
自力退職に伴う現実的なリスク
法律だけでなく、会社の実務的な対応も大きな壁となります。退職届を受け取ってもらえない、上司から執拗に引き止められる、退職理由を何度も問い詰められるといった事例は珍しくありません。
さらに、ブラック企業の場合には「損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」と脅されるケースもあり、退職希望者の心理的負担は非常に大きくなります。このような現実を考えると、自力で即日退職を目指すのはリスクが高く、第三者が介入する退職代行の利用が現実的な選択肢となります。
退職代行が即日退職できないケースを徹底解説

退職代行を利用すれば必ず即日退職できると考える人もいますが、実際には状況によっては難しいケースが存在します。特に雇用形態や業種、法律上の制約によっては、弁護士が介入しても調整が必要になる場合があります。ここでは具体的に「即日退職できないケース」とその背景を解説します。
公務員や特殊な専門職における制約
公務員や医療・福祉・教育などの特殊な専門職は、退職に関して厳格な規定が設けられていることが多く、一般の会社員と同じように「今日から辞めます」とはいきません。公務員法や就業規則で定められた手続きを踏む必要があるため、即日退職を強行すると懲戒処分や損害賠償の対象となるリスクがあります。
会社に重大な損害を与える可能性がある場合
例えば、担当者が退職することで業務がストップしたり、重要な契約や納品が遅れるなど、会社に実質的な損害を与えると判断されるケースです。この場合、会社側が損害賠償を請求する可能性があり、結果として退職者に大きなリスクが発生します。有給休暇を使って即日実質的に退職する方法もありますが、残日数がなければ交渉が必須になります。
民間退職代行業者では対応できない事案
弁護士以外の退職代行業者は、法律上「交渉権限」を持ちません。そのため、未払い賃金の請求や損害賠償に関わる交渉は行えず、「会社から即日退職を認められなかった場合」に強制力を発揮できません。こうしたケースでは、最初から弁護士に依頼する方が安全です。
このように「即日退職できないケース」は少なくありません。即日退職を強く希望する場合は、依頼前に自分の雇用形態や業務内容を整理し、必要であれば弁護士の退職代行を選択することがリスク回避につながります。
即日退職できない民間の退職代行業者の特徴

「退職代行なら即日退職可能」とPRしている民間業者も少なくありません。しかし実際には、法律上の制限や交渉権限の不足により、即日退職ができないケースが多々あります。ここでは、民間の退職代行業者に共通する特徴とリスクを整理します。
民間の退職代行業者は法的代理権がないため交渉ができない
民間業者は弁護士ではないため、法律に基づいた交渉を行う権限がありません。例えば、会社から「損害賠償を請求する」「退職は認めない」と言われた場合、業者は強く反論することができず、依頼者本人が対応を迫られるリスクがあります。この制限が、即日退職を不可能にする大きな要因です。
民間の退職代行業者はブラック企業には効果が薄い
特にブラック企業では、退職代行業者からの電話や書面を軽視したり、高圧的な態度を取って交渉を受け付けないケースが少なくありません。民間業者は法的な強制力を持たないため、会社側が「本人と直接話すまで認めない」と強硬姿勢を崩さないこともあります。その結果、即日退職どころか退職手続き自体が停滞し、依頼者がさらなる精神的負担を抱えるリスクがあります。
民間の退職代行業者は追加費用でトラブルが発生しやすい
基本料金が安く設定されている一方で、「即日対応」「有給消化」「書類交渉」などに別途オプション費用を請求する業者も存在します。その結果、最終的な支払額が高額になったにもかかわらず、即日退職できなかったという相談も少なくありません。料金の透明性が低いことも民間業者の注意点です。
このように、民間の退職代行業者はコスト面のメリットがある一方で、即日退職の実現性やトラブル対応力には限界があります。特にブラック企業のように強硬な姿勢を取る会社に対しては、法的代理権を持つ弁護士の退職代行が圧倒的に有効です。
即日退職できない場合に備える退職代行の選び方

「今日中に辞めたい」と思って退職代行を依頼しても、法律や会社の対応によっては即日退職が実現できないケースがあります。そんなときに備えて重要なのが、トラブルに強い退職代行業者を選ぶことです。ここでは、選び方のポイントを具体的に解説します。
弁護士対応の有無を必ず確認する
即日退職が難しい状況では、法律に基づいた交渉が必要になる場合があります。弁護士が直接対応できる事務所なら、未払い賃金請求や損害賠償への反論といった法的手続きまで一貫して任せられるため安心です。
一方で、民間業者の場合は法律相談や交渉ができないため、結局弁護士を探し直す二度手間になるケースも少なくありません。
料金体系とオプション費用の透明性
民間の退職代行業者の料金は、基本料金が安く見えても「即日対応」「土日対応」「有給交渉」などのオプション費用が重なり、最終的に弁護士と同額かそれ以上になることもあります。事前に見積もりが明確で、追加費用の有無をしっかり確認できる業者を選ぶことが大切です。
退職後のトラブル対応・サポート体制
退職完了後に「備品の返却をめぐるトラブル」や「会社からの嫌がらせ」が発生するケースもあります。こうした事態に備えて、アフターフォローを無料または無期限で提供しているかどうかは、業者選びの大きなポイントです。弁護士法人など専門性の高い事務所であれば、退職後も安心して任せられます。
即日退職を成功させるためには、最初から信頼できる退職代行を選ぶことが不可欠です。特にリスクの高いケースに備えるなら、弁護士による退職代行を選んでおくことで、最悪の事態を避けることができます。
退職代行で即日退職できなかった事例とその解決策
退職代行を利用しても、状況によっては即日退職が難しいケースがあります。ここでは実際の体験談をペルソナ形式で紹介し、どのように解決に至ったのかを解説します。
IT企業勤務/20代後半/男性
民間の退職代行を利用して「即日退職」を希望しましたが、会社から「本人が直接来ない限り認めない」と拒否されました。ブラック企業特有の強硬姿勢で、依頼者は大きなストレスを抱えることに。最終的に弁護士の退職代行に切り替えたことで、会社は法的効力を無視できず、即日退職が成立しました。
サービス業勤務/30代前半/女性
「今日で辞めたい」と強く希望したものの、有給休暇が残っておらず、会社から「2週間は出勤が必要」と言われました。弁護士が介入し、心身の不調を理由とする「正当事由」を主張したことで、即日退職が実現。本人は安心して新しい生活を始めることができました。
製造業勤務/40代前半/男性
退職代行を利用して即日退職を行ったところ、会社から「業務に支障が出た」と損害賠償を請求されました。民間業者では対応できず、途中で弁護士に依頼。弁護士が「退職の自由」を根拠に反論し、損害賠償は棄却されました。即日退職だけでなく、不当な請求からも守られたケースです。
弁護士法人みやびの退職代行は即日退職できない心配が不要!

弁護士法人みやびは古くから退職代行の全国対応をしている法律事務所です。即日退職を強く希望する人に対し、確実かつ安全なサービスを提供しています。弊所では弁護士が直接対応するため、法的に説明して即日退職を実現します。
また、弁護士法人みやびでは、有給休暇の残日数がない場合はその日付けの退職交渉が可能なので、諦める必要はありません。
弁護士法人みやびはLINE無料相談実施中!お気軽に相談を
弁護士法人みやびでは、退職代行及び即日退職を検討している人に向けて、LINEによる無料相談を実施しています。他社で断られた案件や、「いま複雑な状況になってるけど大丈夫?」といったケースも即日退職が可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。
退職代行と即日退職に関するよくある質問
退職代行サービスを検討している方からは、「本当に即日退職できるのか」といった不安の声が多く寄せられます。ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 退職代行を利用すれば必ず即日退職できますか?
必ずしも全員が即日退職できるわけではありません。
有給休暇を消化できる場合や正当事由がある場合は可能ですが、公務員や一部の専門職は規定が厳しく、即日退職が難しいケースもあります。確実に進めたい場合は弁護士対応の退職代行がおすすめです。
Q2. 民間の退職代行業者と弁護士のサービスは何が違うのですか?
民間業者には法的な交渉権限がありません。そのため、損害賠償請求や未払い賃金請求などの法的トラブルには対応できません。
一方、弁護士による退職代行は法律に基づき交渉が可能で、即日退職が難しいケースでも解決に導ける強みがあります。
Q3. 即日退職を希望すると会社に損害賠償を請求されることはありますか?
業務に重大な支障が出る場合や、会社が強硬な姿勢を取る場合には損害賠償を請求される可能性があります。ただし、弁護士が介入することで「退職の自由」を根拠に反論でき、実際に支払いを命じられるケースは稀です。
Q4. ブラック企業でも退職代行は効果がありますか?
民間業者の場合、ブラック企業から「本人と直接話すまで認めない」と突っぱねられるケースがあります。
しかし、弁護士が対応する退職代行なら、会社は法的効力を無視できず、確実に退職手続きを進められます。
Q5. 即日退職を希望しても2週間勤務しないといけないのですか?
民法627条では退職の意思表示から2週間後に労働契約が終了すると定められています。そのため、原則として「即日退職」は難しいとされています。ただし、有給休暇を残している場合はその日から取得し、実質的に出勤せずに退職を迎えることが可能です。さらに、心身の不調やパワハラなど正当事由がある場合は、弁護士の交渉によって即日退職を認めさせられるケースもあります。