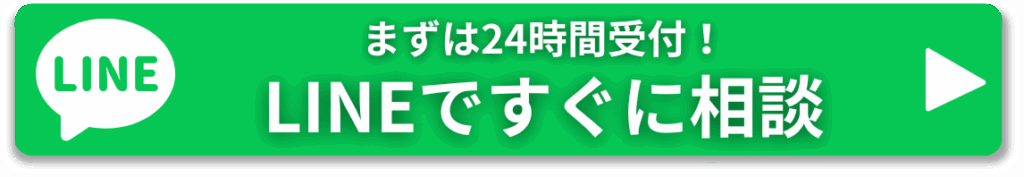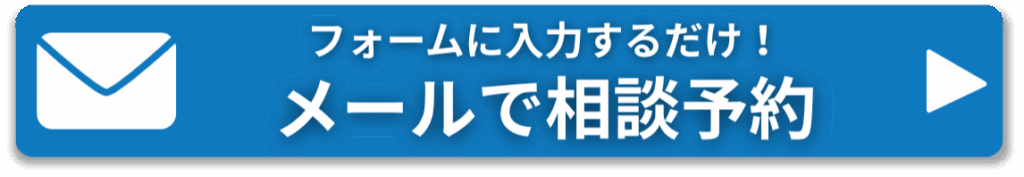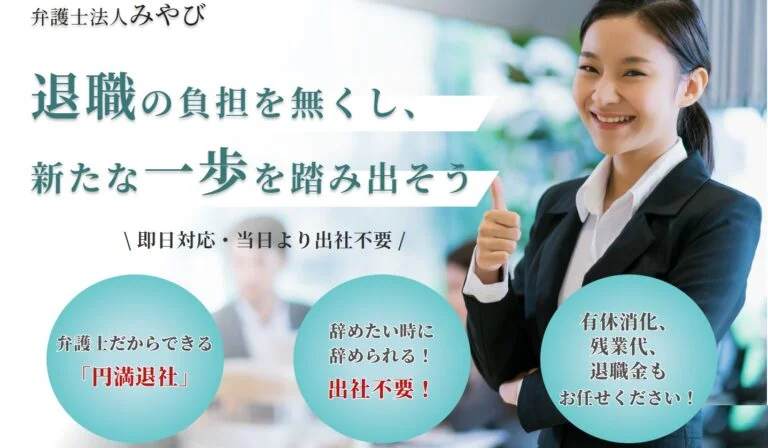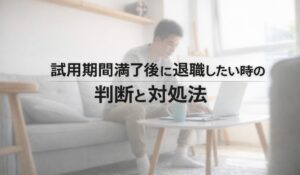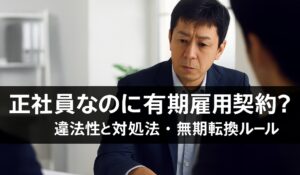退職代行を使っても引き継ぎが必要なケースと不要な場合

近年需要が拡大している退職代行サービスですが、利用を検討している人の中には、「退職代行を使えば仕事の引き継ぎも不要になる」と考えている人が見受けられます。退職代行関連の情報記事を読んでも、「引き継ぎは法的に必要ない」という文言をよく見かけます。
確かに引き継ぎの有無は法的に決まってはいませんが、不適切な退職法や誤った辞め方で引き継ぎをせずに退職してしまったため、会社から損害賠償を請求される事例も発生しています。
ここでは退職代行を使ったときの引き継ぎの有無や、損害賠償請求のリスクなどを解説。詳しくは弁護士法人みやびにご相談ください。
この記事で分かること
- 退職代行を使っても引き継ぎは必要
- 引き継ぎをしなかったため損害賠償請求された事例
- 民間の代行会社だと会社からの電話連絡も無視できない
- 弁護士法人みやびでは引き継ぎは出社不要で最小限に留めることが可能
退職代行を利用した引き継ぎで起こりやすいトラブルとその対応方法

退職代行を利用する際、「引き継ぎは必要ない」と誤解してしまうと、予期せぬトラブルに発展する可能性があります。ここでは、引き継ぎの不備によって起こりやすいトラブルの具体例と、それを防ぐための対応方法を解説します。
引き継ぎの不備で起きる可能性のあるトラブル例
引き継ぎが不十分なまま退職すると、後任が業務内容を把握できず取引先や社内に混乱を招く恐れがあります。例えば、重要な顧客情報が共有されず契約が破棄されたり、社内の業務が滞り納期が遅れる、といった事例があります。場合によっては会社から損害賠償を請求されるリスクもあります。
トラブルを防ぐために知っておくべき対応の基本
トラブルを回避するためには、退職代行を利用しても最低限の情報提供は行うことが重要です。業務の進捗や注意点をまとめた書類を用意し、メールや郵送で提出するだけでも大きな問題を防げます。特に弁護士が行う退職代行であれば、こうしたやり取りも代理してもらえるため、安心して対応が可能です。
退職代行を使えば引き継ぎは不要と言われるわけ

ネットで退職代行の活用記事を確認してみると、「退職代行に依頼すれば引き継ぎも不要」という情報が見受けられます。確かに法律では退職時の引き継ぎの有無の明記はないので、民法627条「退職の意思を会社に伝えた2週間後に会社を辞めることができる」法律を使えば、無期雇用の社員に関してはスムーズに退職できる可能性が高いです。しかし、退職できるからといって損害賠償を請求されないとは限りません。
上記のように、「退職代行を使えば引き継ぎが必要ない」というのは、あくまでも引き継ぎしなくとも強引に退職はできるというだけであり、これをPRする民間の代行業者は、退職完了後に損害賠償請求されるか否かについては、一切触れていないことがほとんどです。
退職代行を使っても仕事の引き継ぎが必要となるケースと過去の判例

上記から分かる通り、退職代行を使うことで法的に会社を辞めることができる一方で、会社から求められた引き継ぎを無視することで、退職後に損害賠償を請求されるケースも過去にあります。
会社が損害賠償を請求できる場合は、往々にして「従業員の退職と会社の損失が直接的関係がある場合」です。従業員が退職代行を使って辞めることに問題はなくとも、①自分の顧客を引き継がなかったため会社が損失を被った、②大事な商談やプロジェクトで自分しか知らない情報を後任に引き継がなかったため、会社が損失を被った、等が挙げられ、過去の判例を見ても場合によって200万円から500万円の支払い命令が命じられた事例もあります。
「人手が足りない」理由で退職後に損害賠償されても支払う必要はない
一方で零細中小企業でありがちな「人手が足りない」理由で退職後に損害賠償を請求されるケースもあります。会社からしてみたら、「貴方が辞めたから仕事が回らなくなって会社が(機会)損失を負った」と言う理由を正当化したいのですが、これに関しては支払う必要はないと考えられています。従業員には職業選択の自由、退職の権利が認められている(民法627条)ので、人手が足りないという会社の人材不足を理由に従業員に対して損害賠償を請求することはできないものと解釈できます。
退職代行と引き継ぎに関する就業規則や人事の対応のポイント

退職代行を利用する場合でも、会社の就業規則や人事部の指示に従うべき場面があります。特に引き継ぎについては、単に法律上の義務だけでなく、社内規程や慣習が影響するため、無視して辞めるとトラブルの原因になることもあります。ここでは、就業規則上の位置づけや人事部の考え方、無視した場合のリスクまで、具体的に解説します。
就業規則における引き継ぎ義務の位置づけ
多くの企業の就業規則には「退職の際は業務の引き継ぎを誠実に行うこと」という規定があります。これは法的な強制力を伴うものではなく、あくまで会社の内部ルールですが、従業員はそのルールを守る義務があります。特に管理職や担当業務が特殊な場合、引き継ぎを怠ると「重大な背任行為」とみなされ、会社から損害賠償請求の材料にされる可能性もあります。そのため、就業規則の内容は必ず確認し、どの程度の対応が必要か把握することが大切です。
人事部が求める一般的な引き継ぎ内容とは
人事部が退職者に求める引き継ぎの内容は、業務内容や役職に応じて異なりますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。顧客情報や案件の進捗状況のリスト化、業務マニュアルの作成、後任への口頭または書面での説明、社内システムや設備の返却などです。特に営業職や専門職では、自分しか分からない知識や人脈が業務に影響するため、これらを共有しないと業務に支障が出てしまいます。退職代行を利用しても、書面やメールでの情報提供であれば十分なケースも多いので、最低限の準備はしておくべきです。
弁護士以外の退職代行サービスは引き継ぎをしないと損害賠償請求のリスクがある。LINEブロックも危険

退職代行サービスは、弁護士以外にも民間業者(一般企業)が提供していますが、引き継ぎの有無が焦点となる場合は、民間業者ではなく弁護士の提供する退職代行を利用してください。昨今は民間業者の中にも労働組合に加盟することで金銭交渉を可能とする業者も増えてきました。しかし、実際に会社から損害賠償請求された場合は、弁護士の有資格者による交渉が必要となるため、労働組合加盟型の退職代行業者では解決ができません。
また、退職代行を依頼した場合、退職日までの期間中は有給休暇の消化に充てるのが通常ですが、民間業者を利用した場合、有休期間中もLINEをブロックしたり、同僚上司からの連絡を無視するのは、後ほどトラブルに発展するリスクがあります。
弁護士に退職代行を依頼すれば会社からの連絡を無視できる理由
弁護士と民間業者の退職代行サービスの大きな違いは、「弁護士は正式な依頼者の“代理”である」ことです。弁護士が退職代行を請け負うと、弁護士は会社に受任通知書を送付します。これにより、弁護士は法的に依頼者の代理となることができ、同僚上司など会社側が依頼者と接触したい場合は、弁護士を通す必要があります。一方で民間業者にはそのような権限がないため、会社に対しては「本人には連絡をとらないようお願いします」としか言えません。

退職代行を使った引き継ぎの方法と会社との交渉の進め方

退職代行を利用する際も、引き継ぎを適切に行わないとトラブルの原因になります。どのように情報を伝え、会社と意見が対立したときにどのように交渉するかが重要です。ここでは、退職代行を通じた引き継ぎの伝え方、会社と揉めた場合の対処法、弁護士を活用した負担軽減の方法について詳しく解説します。
退職代行を通じて引き継ぎを伝える方法
退職代行を利用する場合でも、業務の進捗や顧客情報など、後任が業務を進めるために必要な最低限の情報は必ずまとめておくべきです。一般的には、簡潔なメモや資料を作成して退職代行の担当者に託し、会社へ提出してもらう方法が多いです。弁護士が運営する退職代行なら、内容の確認や提出まで代行してくれるため、本人が出社する必要はありません。書面やメールでの提出でも十分に義務を果たせます。
引き継ぎ内容で会社と揉めた場合の交渉術
会社から過剰な引き継ぎを求められたり、長期間の出社を要求されることがあります。しかし、法的には最低限の引き継ぎを行えば足りるため、過剰な要求は毅然と断る姿勢が大切です。揉めそうな場合は退職代行の担当者を通して、対応できる範囲を明確に伝え、やり取りは必ず記録が残るメールや書面で行いましょう。特に民間業者は交渉権限がないため、トラブルが予想される場合は弁護士に依頼するのが安全です。
弁護士による交渉で引き継ぎ負担を減らす方法
弁護士の退職代行を利用すれば、法律上の代理人として会社と正式に交渉できます。弁護士は就業規則や過去の判例を踏まえ、依頼者が果たすべき最低限の義務を整理したうえで会社に伝え、不当な要求を抑えてくれます。その結果、必要以上の引き継ぎ負担を回避しながら、安全に退職手続きを進めることができ、精神的な負担も大きく軽減されます。
退職代行を使って引き継ぎしたくない。弁護士ならどこでもいい?

退職代行を弁護士に依頼すれば、どの事務所でも同じ成果が得られると思われがちですが、実際には法律事務所によって対応の質や結果には大きな差があります。特に「引き継ぎをしたくない」という希望がある場合、担当する弁護士の実績や交渉力が不足していると、会社の要求に屈して譲歩してしまう可能性もあります。信頼できる事務所を選ぶことが重要です。
弁護士でも引き継ぎトラブルに遭遇することがある。実績豊富な法律事務所を選択しよう
弁護士が担当すれば絶対に安全、というわけではありません。退職代行に慣れていない弁護士だと、会社からの強い要求に押されてしまい、望まない引き継ぎに応じてしまうケースもあります。さらに、事務所によっては低料金の退職代行業務を弁護士ではなく事務員に任せているところもあり、十分な交渉がされないこともあります。引き継ぎトラブルを避けるためには、退職代行の実績が豊富で、弁護士自身が責任を持って交渉してくれる法律事務所を選ぶことが大切です。
引き継ぎは極力避けたい人は「弁護士法人みやび」退職代行の相談を

弊所「弁護士法人みやび」は古くから退職代行業界に参入している老舗の法律事務所です。雇用形態や業種問わず、これまであらゆる退職代行を実施してきました。また、ご相談者様の「引き継ぎは極力したくない」というご要望もしっかりと汲んだ上で最良の方法を模索し、弁護士が直接会社の責任者と交渉します。また、仮に引き継ぎが発生しても、依頼者様は出社の必要はなく、自宅で引き継ぎ資料を作成したのち、郵送による対応となるので、ストレスはありません。
LINE相談は無料!まずはお問い合わせください
弊所「弁護士法人みやび」では、昨今の退職代行の需要拡大に応えるため、LINEによる無料相談窓口を設置しています。「弁護士には問い合わせがしづらいイメージがある」という人はとくにこちらのサービスをご利用ください。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。
退職代行を使った引き継ぎに関するよくある質問
退職代行を利用する際に「引き継ぎは必要か」「損害賠償のリスクはあるのか」「弁護士と民間業者の違いは?」など、よく寄せられる質問と回答をまとめました。安心して退職するためにぜひ参考にしてください。
退職代行を使っても引き継ぎは不要ですか?
法律上、引き継ぎの義務は明記されていませんが、引き継ぎをしないことで会社に損害が発生した場合は、損害賠償請求されるリスクがあります。最低限の情報提供は行うべきです。
引き継ぎをしなかった場合に損害賠償されるケースは?
重要な顧客情報や進行中のプロジェクトを後任に伝えず、会社に損失を与えた場合は、過去の判例でも数百万円の損害賠償が命じられた例があります。
会社から「人手不足」を理由に損害賠償を請求された場合は支払う必要がありますか?
人手不足自体は従業員の責任ではなく、退職の自由は法律で認められています。そのため人手不足だけを理由に損害賠償を請求されても支払う必要はありません。
退職代行を利用する際の引き継ぎ方法は?
退職代行に必要な情報をまとめたメモや資料を作成し、代行業者を通じて提出する方法が一般的です。弁護士が代行する場合は、代理で提出や調整も可能です。
弁護士の退職代行なら引き継ぎを完全に拒否できますか?
弁護士でも、最低限の引き継ぎ義務を完全に無視することは推奨されませんが、過剰な要求や不当な要求を排除し、必要最小限の対応にとどめる交渉が可能です。
弁護士ならどの事務所に依頼しても安心ですか?
弁護士によって実績や交渉力に差があります。退職代行に慣れていない弁護士だと、会社側の強い要求を受け入れてしまう可能性もあるため、実績豊富な事務所を選ぶべきです。
民間業者の退職代行でも大丈夫ですか?引き継ぎ拒否はできますか?
民間業者は法律上の代理権がないため、トラブル時の法的交渉や会社からの損害賠償請求への対応はできません。弁護士に依頼する方が安心です。
LINEブロックなどで会社からの引き継ぎの連絡を完全に無視しても問題ありませんか?
民間業者の場合、本人が無視することでトラブルになるリスクがあります。弁護士に依頼すれば、正式な代理人として会社側との連絡を一任できるので安心です。