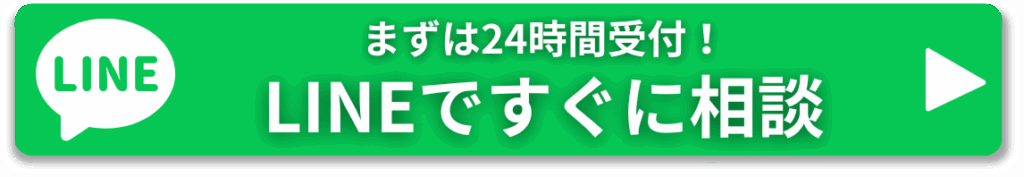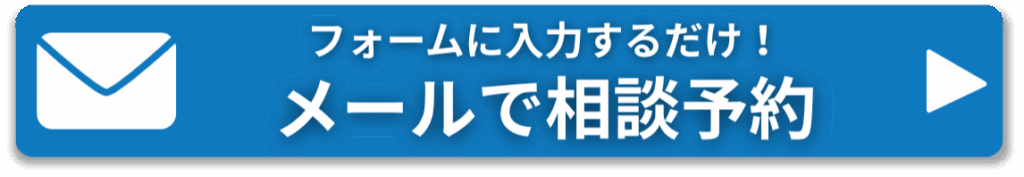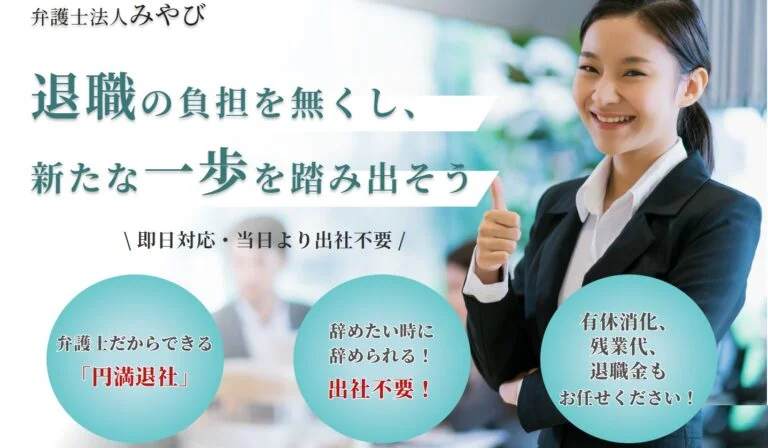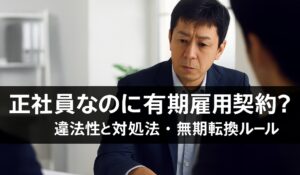退職後に損害賠償された。辞めた会社から請求が届く時の解決法

会社を退職したあと、突然辞めた会社から損害賠償の請求書が届いたら、誰でも驚きと不安を感じます。しかし、無断退職や引き継ぎ不足などを理由に、企業から損害賠償を求められるケースは決して珍しくありません。
ここでは「退職後に損害賠償請求された」、「辞めた会社から請求書が届いた」といったケースをもとに、実際の事例や法律の観点から、どのように対応すべきかを詳しく解説します。
弊所「弁護士法人みやび」では、退職後に損害賠償請求された人はもちろん、「自分の会社はブラックだから、辞めたら損害賠償請求されそう」という人に向けて退職代行を実施しています。まずはLINE無料相談をご利用ください。
退職後に損害賠償請求される典型的な理由と企業側の主張

退職後に突然会社から損害賠償請求されると、驚きと共に大きな不安に襲われます。実際にはどのようなケースで企業側が損害賠償を主張してくるのでしょうか。以下では、その代表的なパターンと背景にある就業規則や法的根拠について解説します。
企業が損害賠償を主張する代表的なケース
企業が損害賠償を求める代表的な事例としては、以下のようなものがあります。
- 事前連絡なく無断退職したことによって業務が停止した
- 引き継ぎがなされず、クライアントや社内に多大な混乱をもたらした
- 機密情報を漏えいしたことにより損害が発生した
- 就業規則や雇用契約に明確な違反行為があった
これらはいずれも「退職後の義務違反」に該当しうるものであり、企業は民法や就業規則を根拠に請求を行ってきます。
退職後の業務放棄・引き継ぎ不備は損害賠償につながる?
引き継ぎの放棄によって損害が生じた場合、企業側が「相当の損害」を主張し損害賠償を求めることがあります。ただし、退職者の責任が法的に認められるかどうかは、実際に損害が発生したかどうか、就業規則に明文化されていたかなど、多くの条件が絡みます。
実際の裁判では、「退職者に明確な故意や過失があったかどうか」が重要視されます。
そのため、ただの引き継ぎ不足では賠償責任が問われないケースも多く、専門的な判断が必要になります。
辞めた会社から突然届く請求書|退職後に想定される金額と請求内容の実例

退職後、企業から突然請求書が届くケースは少なくありません。多くの場合、法知識のない社長の嫌がらせに留まりますが、辞めた従業員にとっては焦りますし、対応するだけでも精神的に疲弊します。
退職後に届く請求書の内容とは?
企業からの請求書には「業務放棄による損害」や「機密情報の漏洩による損害」などが記載されることがあります。これらの内容には明確な証拠が伴っていない場合も多く、法的に無効であることもあります。内容に不明点がある場合は、返答する前に弁護士に相談することが大切です。
損害賠償請求の金額はどれくらいが相場?
金額はケースバイケースですが、数万円から数十万円まで幅があります。中には数百万円にのぼる請求もありますが、根拠が曖昧なケースも多く、支払う義務があるとは限りません。請求額に対して適切に対応することが、リスク回避のカギとなります。
退職後の損害賠償請求に関する就業規則とその法的有効性

企業の就業規則には、損害賠償に関する条項が設けられていることがあります。これにより従業員が退職時や退職後に賠償責任を負うよう記載されている場合がありますが、法的にはそれが必ずしも効力を持つわけではありません。
就業規則の損害賠償条項はどこまで効力がある?
損害賠償に関する就業規則は、労働契約法や民法に基づき一定の効力を持ちます。ただし、その条項が合理的かつ具体的である必要があります。例えば、従業員の故意または重過失により損害が発生した場合のみ、賠償義務が認められることが一般的です。曖昧な表現や過剰な責任を課す内容であれば、裁判では無効とされる可能性もあります。
就業規則にサインしている場合の注意点
就業規則にサインしたからといって、すべての条項に無条件で従う義務が生じるわけではありません。特に損害賠償に関する条項は、労働者にとって一方的に不利な内容であることも多く、実際のトラブルでは法的な精査が重要となります。サインの有無よりも、条項の内容とその合理性が重視されます。
退職後の会社からの損害賠償の請求が違法になるケースと従業員の権利
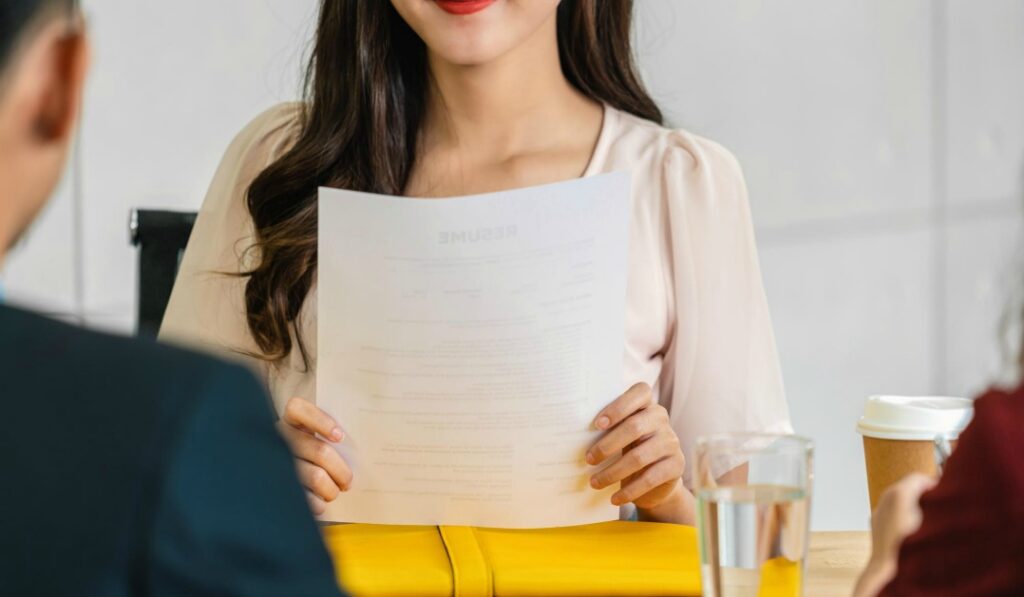
違法な損害賠償請求として最も多く見られるのは、従業員が退職したこと自体に対する請求です。たとえば「突然辞めたことで業務に支障が出た」として高額な賠償を求める例は、明確な損害や因果関係が証明されない限り、法的には認められません。
また、就業規則に「損害賠償を請求する」と明記されていても、それがすべてのケースで有効とは限らない点も注意が必要です。 一方的に高額な賠償金を請求する行為は、パワハラや嫌がらせとみなされる可能性もあります。
労働者の権利として主張できること
労働者は、退職の自由を憲法や労働基準法で保障されています。 そのため、企業が不当に損害賠償を請求してきた場合には、法的に対抗する権利があります。 労働者は「民法第627条」により、2週間前に退職の意思表示をすれば自由に退職できる権利があります。 加えて、違法な請求を受けた場合には、労働基準監督署や弁護士に相談し、法的に対抗し、逆にこちら側が精神的苦痛に伴う慰謝料を請求することが可能です。
退職後に損害賠償請求される理由:誓約書・競業避止義務違反のリスクと判決の傾向

退職後に損害賠償請求された場合、よく問題となるのが「誓約書」や「競業避止義務違反」です。そもそも誓約書とは、退職時や在職中に会社と従業員の間で交わされる約束事を文書化したものです。多くの場合、「機密情報の持ち出し禁止」、「退職後の一定期間は同業他社への就職・開業をしない」といった内容が盛り込まれます。
この誓約書や競業避止義務に違反した場合、損害の有無や範囲を巡って争いが生じます。ただし、企業側が損害を主張するには、実際に経済的な被害が発生したことを証明しなければなりません。一方で、誓約書の内容が極めて合理的であったり、明確に売上減少や顧客流出などが認められた場合は、損害賠償命令が下ることもあります。誓約書の合理性は素人では判断が難しいので、すでにサインしてしまっている場合は、速やかに弁護士に相談するのが良いでしょう。
判決事例にみるリスクの判断ポイント
裁判所の判決では、「競業避止義務が合理的範囲内かどうか」、「損害額の算定方法」、「違反行為と損害の因果関係」などがポイントとして争われます。
競業避止義務の合理性は、主に「限定した地域と期間、業界・業種の特定」が具体的に必要です。「退職後5年間は競合他社に転職してはいけない」といった抽象的で具体性のない誓約書では、ほぼ無効となります。
機密情報や引き抜きによる退職後の損害賠償請求への対処法と企業法務のポイント

退職後に損害賠償請求された場合、「機密情報の持ち出し」や「顧客・従業員の引き抜き」が大きなトラブルの原因となることが少なくありません。IT業界や医療分野、コンサルティング業などは、社外秘の情報や顧客リストの流出が直ちに経営上の損害につながるため、企業側の対応も厳格です。
近年では、USBメモリやクラウドサービスを使ったデータの持ち出しなど、事件性の高い事案も増加しています。また、退職者が取引先や現職の社員を新しい職場へ引き抜いた場合も、企業側は損害賠償請求や訴訟に発展させることがあります。
大手企業は企業法務に敏感で、顧問弁護士もいるため、誓約書もしっかり作り込まれているのが昨今の傾向です。もし退職時に会社から損害賠償請求された場合は、まずは一人で示談交渉に臨まずに、法律の専門家にアドバイスを貰うのがおすすめです。
裁判に発展した退職後の辞めた会社からの損害賠償請求の事例とその結果

損害賠償請求が企業と労働者間で解決されない場合、裁判に発展するケースもあります。裁判は時間と費用がかかるうえ、判決によっては企業側・労働者側どちらにとっても不利益をもたらすことがあります。
過去にあった退職後の損害賠償請求の実例
実例として有名なのは、従業員が退職直前に重要なプロジェクトを放棄し、企業が数百万円の損失を被ったとして訴訟に至ったケースです。この裁判では、企業側が損害額と因果関係を立証できなかったため、最終的に請求は棄却されました。
他にも、顧客情報を無断で持ち出したとして、企業が元従業員を訴えたケースでは、情報漏えいの証拠が認められ、賠償命令が下された事例もあります。
企業と労働者、どちらが勝ったのか
全体的に見て、企業が損害賠償請求で勝訴するには、明確な証拠と法的根拠が求められるため、判決では労働者側が有利となるケースが多いです。
退職の自由や、引き継ぎ義務の法的な制限を理解せずに企業側が請求を行った場合、裁判所はその請求を退ける傾向にあります。
一方で、情報漏洩や背任行為などの明確な不法行為が確認された場合には、企業側が勝訴する可能性もあります。IT業界では昨今この手の訴訟問題が多く、また企業側が勝訴した際、かなりの額の賠償請求の支払い命令が下されることもあります。
退職後に辞めた会社からの損害賠償請求問題で弁護士に相談すべきタイミング

企業が損害賠償請求に至る背景には、秘密保持違反や競業避止義務違反などの企業法務上の問題が絡んでいるケースがほとんどです。また、在職中に研修や引き継ぎが不十分だった場合なども、損害発生の理由として挙げられることがあります。
退職後に企業から損害賠償請求された場合は、慌てて連絡や謝罪をする前に、まずは事実関係や証拠資料を整理し、なるべく早い段階で労働問題専門の法律事務所(弁護士)に相談しましょう。
場合によっては、請求自体が無効となる可能性や、実際には損害が発生していない事案も少なくありません。不当な請求や納得できない損害賠償が届いた際は、法律事務所などの専門家への依頼を早めに検討しましょう。プロフェッショナルによるアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑えた上で、適切な対応策を立てることができます。
相談時に用意しておくとよい証拠や資料
弁護士に相談する際は、請求書や在職時の誓約書・契約書、メールやチャットなどの証拠資料を持参しましょう。弁護士費用や依頼の流れについても事前に説明を受け、納得した上で進めることが重要です。複雑な案件の場合は、複数の法律事務所にセカンドオピニオンを求めるのも有効な方法です。
いずれにせよ、専門家と一緒に「本当に支払い義務があるのか」、「支払いを最小限に抑えるための方法」を冷静に検討しましょう。
弁護士に相談する際は、以下のような資料を準備しておくとスムーズです。
- 請求書や内容証明のコピー
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 退職届の控え(提出した場合)
- メールやLINEなどでのやりとり記録(上司・人事とのやりとり)
- 就業規則の写し
これらは弁護士が法的対応を検討する上で重要な証拠となります。
退職代行を使って辞めた人が退職後に損害賠償請求される可能性は?

退職代行サービスを利用した人でも、辞め方によっては損害賠償のリスクが発生します。引き継ぎを行わず即日退職した場合や、退職理由が曖昧であった場合には、会社側が請求の正当性を主張することもあります。
民間の代行業者に依頼した人の中には「退職は完了できたけど、その後に会社から損害賠償の請求書が来た。業者に相談しても『弁護士に相談してください』と言われ取り合ってもらえなかった」という相談者もいました。
退職代行利用者が訴えられたケースはある?
実際に、民間の退職代行業者を使って退職したあとに、引き継ぎ不備や損失発生を理由に企業から損害賠償請求された例も報告されています。
一方、弁護士が対応したケースでは、企業側が法的対抗策を取りづらいため、訴訟に至ることは非常に稀です。
退職後の損害賠償が不安なら弁護士法人みやびの無料相談を

弊所「弁護士法人みやび」には労働問題専門の弁護士が在籍しています。退職代行と合わせて損害賠償問題を解決することもできますし、退職後の損害賠償請求の解決のみのご依頼も可能です。LINEで無料相談が可能なので、気軽にご利用いただけます。
弁護士法人みやびは無料の手厚いサポートが特徴
弁護士法人みやびでは、LINEによる無料相談サービスを提供しているほか、退職代行をご依頼いただいたすべての人に向けて「無料の転職サポート」、「退職後の無期限アフターサポート」を提供しています。
単に退職手続きを完了させるだけでなく、退職後に会社から損害賠償請求を受けた場合にも対応可能なため、ご依頼者様は退職前から退職後まで一貫して安心してお任せいただけます。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。
損害賠償請求が無効となるケースや訴訟への発展を防止するための対策

退職後の損害賠償請求は、必ずしもすべてが有効というわけではありません。会社側が感情的になり、根拠の薄い請求を行っている場合や、単なる嫌がらせ・脅しのケースも少なくありません。
また、損害賠償請求の内容が理不尽であったり、合理性に欠けているケースも多く、実際に裁判まで発展することが想定されていない損害賠償請求が実は多いです。実際の訴訟に発展するのはごく一部で、多くは請求内容が見直されたり、当事者同士で話し合いによる解決が図られます。ただし、法知識のない素人の場合は、会社から突然高額な請求をされると、そのプレッシャーからすぐに謝罪したり、減額交渉をしてしまい、本来支払う必要のないお金まで支払ってしまうこともあります。
退職後の損害賠償においては、企業側の要求を鵜呑みにする前に、まずは弊所「弁護士法人みやび」にご相談ください。