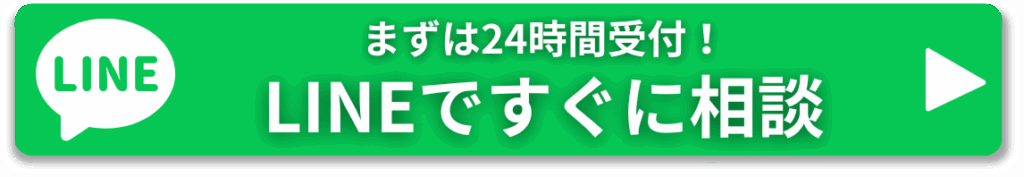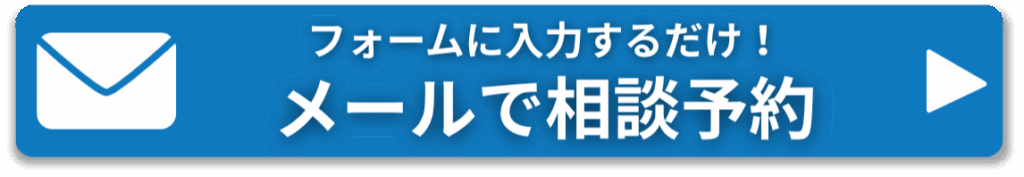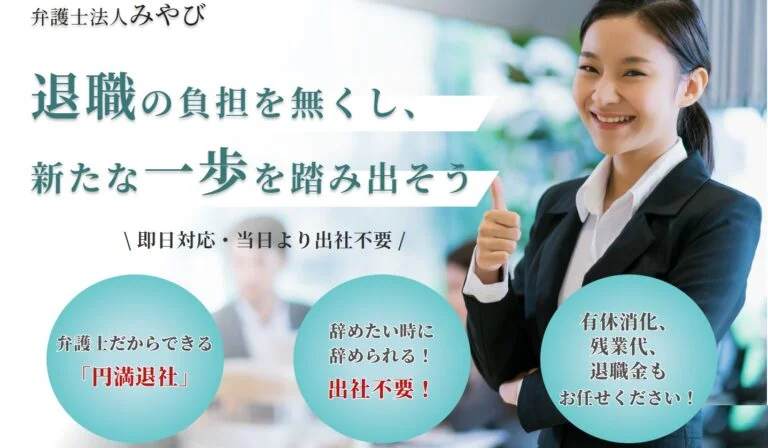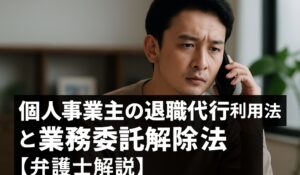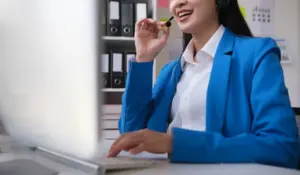代行事例│飲食店の店長を家庭の事情を理由に即日退職を実現

都内勤務の飲食店に勤める男性からのご相談。弁護士が責任者と交渉して本来困難な即日退職を実現しました。
東京都内の飲食店で働く店長の方からの依頼で退職代行を実施しました。店長職に就く青木様(仮名)は日ごろから管理者のパワハラに悩んでおり、退職を考えていました。そして、この度母の介護といった“家庭の事情”を理由に1日も早い退職を決意し、弊所「弁護士法人みやび」にご依頼いただき、弊所在籍の弁護士による介入を経て即日退職を実現しました。
飲食店の雇われ店長(オーナーではなく雇用契約を結んだ従業員)の中には、オーナーや上司のパワハラに悩んでいる人が多く、近年は退職代行の認知度の向上により、弊所への問い合わせも日増しに増えている印象です。
弊所「弁護士法人みやび」では、退職代行を検討している全国の飲食店の店長様に向けて、LINEによる無料相談窓口を設置しています。是非お気軽にご相談ください。
飲食店・店長からの相談:上司からのパワハラと長時間労働が常態化

東京都内に勤める飲食店の店長職に従事する男性からのご相談。男性は雇われ店長の身として就業しており、日ごろからオーナーや自分の上司(管理者)から高圧的な言葉やプレッシャーをかけられ、パワハラに悩んでいる状態でした。
また、週に70時間勤務を強いられることも頻繁にあり、休みもろくにとれない劣悪な労働環境下に置かれており、早期の退職を検討していました。その中で、母の介護が必要となる問題が急遽発生し、上司に1日も早い退職を求めましたが拒否され、この度弊所にご相談の上、正式に退職代行をご依頼いただきました。
退職代行実施前のポイント:飲食店店長の即日退職は法的リスクの確認が重要

ご依頼を受けた後は、飲食店の店長様が勤める会社の就業規則を確認しました。その中の退職規定では、「退職する場合は1か月前に予告しなければならない」旨の記載がありました。
通常、正社員の場合は、雇用契約を交わすと同時にこのような労働契約や就業規則の制限が設けられるのが普通です。法的に一方的な退職を実現したい場合は民法627条(退職の意思を伝えた2週間後に労働契約が解除される)が有効ですが、今回の場合は2週間待たずに即日退職を希望されているため、弁護士による交渉が必要でした。
一方で即日退職を実行する場合は、法的リスクを鑑みなければなりません。就業規則に記述のある退職1か月前の予告には合理性があるため、なるべく従う必要があるかと存じますが、特別な事情がある場合はその限りではありません。弊所では、今回ご依頼者様の「長時間労働」や「家庭内環境の変化」が即日退職をする十分な理由であると判断し、弁護士の有資格者が先方の責任者と直接電話にて交渉しました。
民間業者(一般企業)の退職代行では失敗のリスクもある
退職代行は民間業者(一般企業)と弁護士事務所がサービスを提供していますが、十分な法知識のない民間の代行業者に依頼してしまうと、上述した民法や労働法を不作法に行使してしまい、トラブルの元となります。「即日退職を依頼したが叶わず2週間の出社を余儀なくされた」、「退職はできたけど賠償金を請求された」といった失敗リスクも報告されています。
退職とは法的な労働契約解除手続きを指します。第三者に仲介や交渉を依頼するのであれば、労働法に精通した法律の専門家に依頼すべきと言えるでしょう。
退職代行の実施と結果:弁護士の介入により飲食店店長の即日退職を実現

弊社在籍の弁護士によりご依頼者様の上司に電話し、即日退職の交渉を行いました。当初は先方も拒否反応を示していましたが、違法性の高い長時間労働の指摘と家庭の事情を正当な退職理由として説明することで、弁護士からの直接交渉もあってか相手の責任者も最終的には丁寧な対応でこちらの言い分をすべて呑んでくれました。
結果的に本日をもってして即日退職を実現。健康保険証、制服、社員証、ノートパソコンといった会社の備品は郵送にて返却手続きをしました。こちらに関しても弊所がしっかりとサポートしております。また、会社から退職届の提出を要求されましたので、こちらに関してもご依頼者様が不明な部分等詳細をお伝えし、退職完了まで躓くことのないようサポートさせていただきました。
飲食店店長の即日退職は弁護士法人みやびへご相談を。あらゆるトラブル解決します

飲食店の店長はお店の経営や人材・従業員管理を担当しているため、本来であれば他業者と比較して即日退職は難易度が高い業種となります。
しかし、弊所「弁護士法人みやび」では、長年の退職代行の実績を持つ労働問題専門の弁護士が適切に介入することで、法的リスクを最小限に抑えて即日退職の交渉が可能となります。また、退職に伴う残業代やパワハラの慰謝料請求なども対応可能です。他社・他事務所で断られた案件も請け負える可能性がございますので、まずはお気軽にご相談ください。
飲食店の店長が辞めたいと思う5つの理由

飲食店の店長として働いていると、やりがいを感じる一方で、様々な理由から「もう辞めたい」と思うことがあるでしょう。実際に弊所(弁護士法人みやび)には多くの飲食店店長から退職の相談が寄せられています。
ここでは、飲食店の店長が退職を考える主な理由を5つ紹介します。
飲食業界のあるある?店長が受ける上司や経営者からのパワハラ問題
飲食業界では、残念ながら今でもパワハラが横行しているケースが少なくありません。弊所に寄せられる相談の中でも、特に多いのが上司(エリアマネージャーなど)や経営者からのパワハラです。
「売上が目標に達しないと、毎日のように怒鳴られる」
「スタッフのミスを全て自分の責任にされる」
「売上とレジ金が合わないと自分の給料から補填される」
このような行為は明らかなパワハラであり、精神的健康を著しく損なう可能性があります。また、2020年6月からはパワハラ防止法が施行され、会社には従業員をパワハラから守る法的義務が生じています。飲食店の店長であっても、不当なパワハラに耐える必要はありません。
【相談事例】都内の人気飲食チェーン店長A氏(32歳):「エリアマネージャーからの日常的な暴言や威圧的な態度に耐えられなくなりました。精神的に追い詰められ、毎日出社が憂鬱でした。」
飲食業界の社会問題:店長の長時間労働と休日出勤の常態化
飲食店の店長として最も悩まされるのが、長時間労働と慢性的な人手不足による休日出勤の常態化です。法律で定められた労働時間を大幅に超える「サービス残業」を強いられるケースも多く見られます。
「月の残業時間が100時間を超えることもある」
「スタッフが急に休むと、当たり前のように休日でも呼び出される」
「開店準備から閉店作業まで、実質12時間以上の勤務が当たり前」
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働には割増賃金の支払いが義務付けられています。また、月80時間を超える残業は「過労死ライン」とされており、健康被害のリスクが非常に高くなります。自分の健康を守るために、このような環境からの退職を考えることは当然の権利です。
【相談事例】関西の居酒屋店長B氏(28歳):「月の休みは4日程度で、それ以下のときもある。実質的に週70時間以上の勤務が続いていました。体調を崩して病院に行くと『自律神経失調症』と診断され、このままでは健康に重大な影響が出ると警告されました。」
店長の激務:スタッフ管理の負担とストレス
飲食店の店長は、料理の品質管理やサービス向上だけでなく、アルバイトやパートを含む多様なスタッフの採用・教育・シフト管理まで担当することが一般的です。この人材管理が大きなストレス源となっているケースが多く見られます。特に近年は飲食業界全体で人手不足が深刻化しており、店長一人の肩にかかる負担は増すばかりです。
【相談事例】東北地方のファミレス店長C氏(35歳):「常に5〜6名のスタッフが不足した状態での運営を強いられ、自分自身もホールやキッチンに入らざるを得ない状況でした。管理業務は結局深夜や休日にこなすことになり、プライベートがほぼ皆無になっていました。」
給与や待遇面での不満
飲食店の店長は責任の重さの割に、給与や待遇が見合っていないと感じる方が非常に多くいます。特に中小規模の飲食店では、店長といえども給与水準が他業種と比較して低い傾向にあります。
「店長になっても月給25万円程度で、残業代も出ない」
「売上ノルマだけが厳しく、インセンティブ制度や残業手当、休日出勤手当がない」
「社会保険や福利厚生が不十分」
厚生労働省の統計によると、飲食店の店長職の平均年収は他業種の管理職と比較して約20〜30%低いという現実があります。また、名ばかり管理職として残業代を支払われないケースも多く、これは労働基準法違反となる可能性があります。
【相談事例】関東の焼肉店店長D氏(30歳):「店長として月商1,000万円の店舗を任されていましたが、基本給は22万円で残業代は一切支給されず、諸々の手当がついても月の手取りは25万円ほど。既に30代後半でこの給料。休みも少なく、時給換算すると最低賃金を下回る計算になりました。」
店長以上の役職が詰まっている:飲食はキャリアアップの限界を感じることが多い
飲食店の店長として数年働いた後、「このまま同じ仕事を続けていくべきか」というキャリアの壁に直面する方も多くいらっしゃいます。特に成長志向の強い方は、自分のスキルや経験を活かせる新たなステージを模索することがあります。
「店長以上のキャリアパスが見えない」
「会社が小規模経営で、管理職は一族で埋まっている」
「独立や異業種への挑戦を考えている」
飲食業界でのキャリアは、店長から複数店舗の統括マネージャー、エリアマネージャーへと進む道もありますが、ポジションは限られています。また、30代、40代になったときの将来像が描きにくいという声も少なくありません。自分の成長や将来のキャリアを見据えて、今の環境を見直すことは非常に重要です。
【相談事例】九州のカフェ店長E氏(29歳):「5年間店長を務めましたが、このまま同じ仕事を続けていくことにモチベーションを感じられなくなりました。自分のマネジメント経験を活かして、異業種にチャレンジしたいと考えています。」
飲食店の店長職を辞めたいけど転職先が心配:退職後のキャリアパスを紹介

飲食店の店長職を辞めた後、次のキャリア選択に迷う方は多いものです。しかし、店長として培ったスキルや経験は、飲食業界はもちろん他業種でも高く評価されることが増えています。
飲食業界内での転職
店長経験者は飲食業界内で即戦力として重宝されます。大手チェーンでは労働環境の改善やキャリアパス明確化が進み、待遇も向上傾向です。前職での売上改善やマネジメント実績など、具体的な成果をアピールできると有利です。
他業種への転職
店長経験で培った顧客対応力やマネジメント力は、小売・アパレル・営業職など様々な業界でも通用します。実際に店長から異業種の店舗管理職やサービス業へ転職し、すぐに責任ある立場を任されるケースもあります。
ワークライフバランスを重視した働き方
健康や家庭の事情を優先したい場合は、アルバイトや短時間正社員、副業など柔軟な働き方も選べます。店長経験が評価され、一般のアルバイトより高い時給や好条件で採用されることもあります。
飲食店店長が退職する際の3つの注意点
飲食店店長が円満に退職するためには、「退職時期の選び方」「引継ぎ」「退職理由の伝え方」の3点が特に重要です。
飲食店店長を辞めたい人が退職する際の3つの注意点

飲食店の店長として働いていると、長時間労働や人間関係の悩み、家庭の事情など、さまざまな理由で「辞めたい」と考えることもあるでしょう。実際、退職時期や引継ぎの方法、退職理由の伝え方などを誤ってしまうと、店舗やスタッフに迷惑をかけてしまうだけでなく、トラブルや不利益を招くリスクもあります。
ここでは、飲食店店長が円満に退職するために特に気を付けておきたい「3つの注意点」について、実務経験や法律の観点も踏まえて詳しく解説します。これから退職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1. 飲食店店長の退職時期の選び方
退職のタイミングは、店舗運営や自身のキャリアに大きく影響します。繁忙期(年末年始やGWなど)は避け、月初や月末を狙うと手続きがスムーズです。引継ぎ期間として1〜2週間を目安に、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。就業規則上「退職予告は1ヶ月前」などの定めがあっても、民法では2週間経過で退職可能です。ただし、突然の退職は避け、円満に進める配慮が必要です。
2. 飲食店店長の引継ぎポイント
店長職は重要なポジションなので、計画的な引継ぎが欠かせません。
業務マニュアルやパスワード、取引先リスト、スタッフ情報などを整理し、後任者やスタッフへ丁寧に説明しましょう。常連客や取引先にはできるだけ直接挨拶をすることで、円満な退職につながります。
自分の義務を果たした記録も残しておくと安心です。
3. 飲食店店長の退職理由の伝え方と法的リスク回避
退職届は必ず書面で提出し、手続きや引継ぎ内容は記録に残しておくことが大切です。メールで退職せざるを得ない状況にある場合は、送信内容は記録できるようにしておきましょう。社内メールを使った場合、会社側がアクセスを遮断して過去メールが見れなくなってしまうことがあるので、個人のパソコンから送るのがおすすめです。パワハラなどの問題がある場合は証拠を残し、即日退職が必要な際は専門家への相談や医師の診断書の準備も検討しましょう。
まとめ:飲食店店長が後悔しない退職を実現するためのポイント

飲食店の店長が退職を考える際は、早く現状から抜け出したいという気持ちと同時に、「本当にこの判断で良いのか」、「退職後の生活は大丈夫だろうか」といった不安もつきものです。しかし、事前の準備と適切な手順を踏むことで、トラブルを回避し納得できる新しいスタートを切ることが可能です。
退職前に確認すべきチェックリスト
店長職を退職する前に、以下のチェックリストを参考にして、漏れのない準備を心がけましょう。
・就業規則や雇用契約の退職条件を確認
・退職時期やスケジュールの決定
・後任やスタッフへの引継ぎ準備(業務マニュアル、取引先リスト、パスワード等の整理)
・会社備品や制服などの返却方法の確認
・退職理由や挨拶の伝え方を考えておく
・退職後のキャリアプラン・転職先のリサーチ
このような準備を事前に済ませておくことで、余裕を持って退職日を迎えることができます。
法的トラブルを避けるための準備
円満退職を実現するためには、法的な観点からも注意が必要です。
・退職届は必ず書面で提出し、控えを手元に残す
・退職手続きや引継ぎの記録はメールなどで残す
・就業規則や労働契約の内容は事前に確認しておく
・パワハラや残業代未払いなど問題があれば、証拠(メール・LINE・診断書等)を保存
・万が一、トラブルに発展した場合は、速やかに専門家へ相談
これらを意識することで、不要なトラブルや法的リスクから自分を守ることができます。
弁護士法人みやびへの相談方法
もし退職手続きや職場との交渉に不安がある場合は、専門家である弊所弁護士法人みやびへの相談をおすすめします。弁護士法人みやびでは、LINEや電話での無料相談窓口を設けており、全国どこからでも気軽に問い合わせが可能です。
「すぐにでも辞めたい」、「パワハラで困っている」、「退職金や残業代の請求も相談したい」といった悩みにも的確に対応できますので、迷ったときはまず弊所に相談してみてください。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。