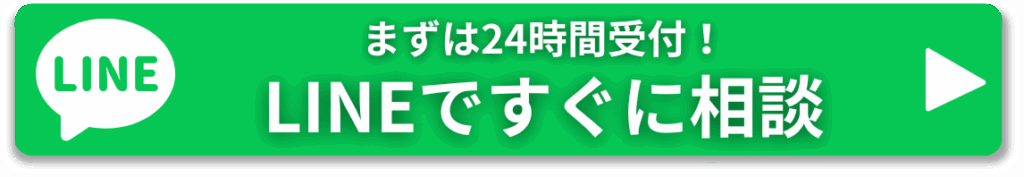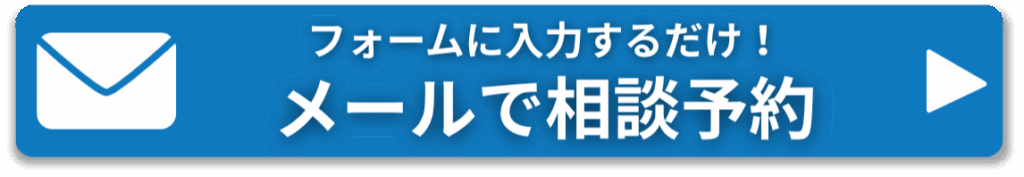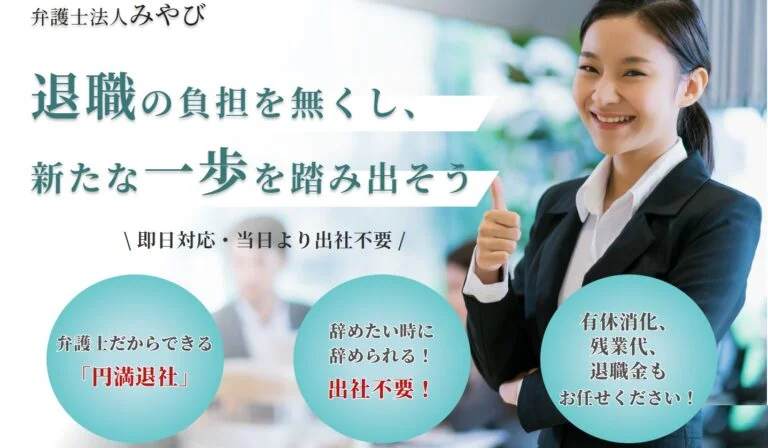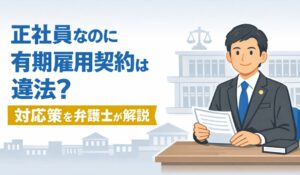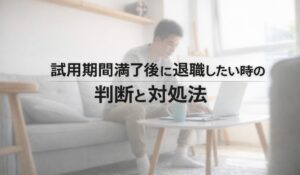正社員なのに有期雇用契約?違法性と対処法、無期転換ルール
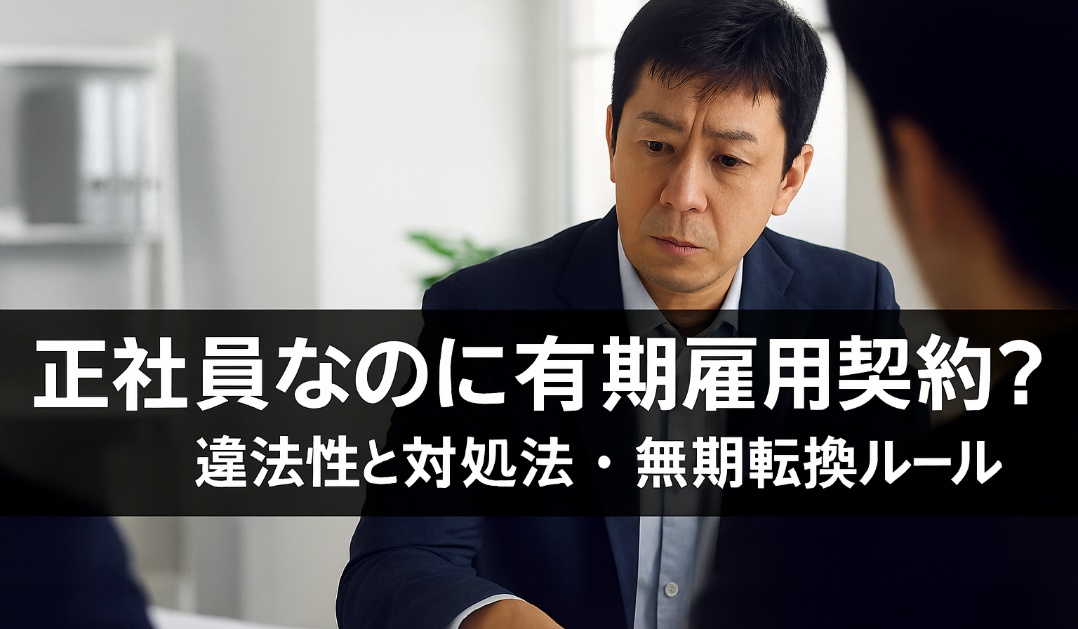
「正社員として採用されたはずなのに、有期雇用契約を渡された」「正社員として就職して、契約期間があるなんて聞いていない」――こうした相談が近年増えています。正社員という言葉には法律上の定義がなく、企業ごとに運用が異なるため、求職者が誤解しやすい点でもあります。
本記事では、正社員なのに有期雇用契約を結ばされるケースの違法性、労働契約法のポイント、無期転換ルール、企業側の意図、そしてトラブル発生時の対処法まで専門的に解説します。弁護士法人みやびが実務で扱う相談内容をもとに、今あなたが取るべき行動を明確にお伝えします。
弊所「弁護士法人みやび」は退職代行サービスを全国に提供しています。会社をトラブルなしで退職したい、という方は、ぜひLINE・Emailよりご相談ください。
正社員なのに有期雇用契約とは?定義と誤解されやすいポイント

最初に「正社員」と「有期雇用契約」という二つの言葉のズレを理解することが重要です。日本では正社員に明確な法律上の定義がなく、企業によって運用が異なります。そのため、求人内容や採用面談で「正社員採用」と聞いていても、実際には有期雇用契約が提示されるケースがあります。ここでは雇用形態の構造を整理し、何が問題になるのかを解説します。
有期雇用契約と無期雇用契約の根本的な違い(労働契約法の基礎)
有期雇用契約は雇用期間を明示して締結する契約で、契約期間が満了すれば更新または終了となります。一方、無期雇用契約は期間の定めなく継続するため、雇止めリスクがありません。正社員は一般的に無期雇用として扱われることが多いですが、法律上「正社員=無期雇用」と明記されているわけではなく、この曖昧さがトラブルの原因となります。
正社員という呼称に法律上の定義がない理由と企業側の狙い
「正社員」という言葉は企業が独自に使う呼称であり、労働基準法や労働契約法には定義が存在しません。そのため、企業が「正社員採用」と説明しながら実際には契約期間を設け、有期雇用契約を渡すことも形式上は可能です。背景には人件費管理、人事制度の柔軟化、雇止めリスク回避など企業側のメリットがあり、求職者が不利益を被るケースが少なくありません。
契約社員との違いが曖昧になりやすいケース
求人票に「正社員(契約期間あり)」と表記されていたり、試用期間中のみ契約社員扱いとする企業もあります。しかし、実態は契約社員と同じ働き方を求められながら待遇が異なる場合、不合理な労働条件として争点になることがあります。特に待遇差、昇給制度、更新ルールが曖昧なときは注意が必要です。
正社員に有期雇用契約を結ばせるのは違法か?労働契約法と労基法から徹底解説

「正社員として採用したのに契約期間があるのは違法では?」という相談は非常に多いです。結論として、法的に認められるケースと認められないケースが存在します。ここでは労働契約法や労働基準法をもとに、企業が有期雇用契約を提示する際に何が問題になるのかを整理して解説します。特に試用期間、人事部の説明義務、雇用条件の明示は重要な判断材料となります。
試用期間を理由に有期雇用契約を使う場合の許容範囲と注意点
企業は「まずは試用期間だから」という理由で有期雇用契約を提示することがあります。試用期間自体は合法ですが、試用期間を理由に不合理な労働条件を設定したり、本採用後も有期のままにする場合は問題となる可能性があります。労働契約法第16条では、解雇や契約終了の合理性が厳しく問われるため、企業側にも明確な説明義務があります。試用期間中でも契約内容に疑問を感じた場合は、早めに確認することが必要です。
無期雇用から有期雇用へ変更する「逆転雇用」の違法性
採用時に無期雇用の説明を受けていたにもかかわらず、契約締結時に有期雇用契約へ変更されるケースがあります。これは一般に「逆転雇用」と呼ばれ、労働契約法違反となる可能性が高い行為です。雇用期間を後から付け加える行為は、労働者の同意があっても無効と判断されるケースがあります。また、人事部が「正社員だけど最初の1年だけ有期」などと説明した場合でも、法的には無期として扱われる可能性があります。
労働条件明示の義務違反と不合理な労働条件の判断基準
企業は労働基準法第15条に基づき、契約期間、業務内容、待遇などの労働条件を明示する義務があります。正社員として採用したと説明しながら有期雇用契約を提示した場合、説明不足や虚偽説明としてトラブルにつながりやすいです。また、給与や福利厚生などで正社員と契約社員の違いが不合理に広がっている場合は違法性が疑われます。疑問点がある場合は契約書と求人内容を照らし合わせることが重要です。
正社員が有期雇用契約にされたときに起こりやすい問題と実例

正社員として採用されたにもかかわらず有期雇用契約を提示されると、待遇差や契約更新リスクなど複数の問題が発生します。企業側には人件費や契約管理のメリットがありますが、労働者側は雇用が不安定になり、キャリア形成にも影響します。ここでは実際の相談ケースとともに注意すべきポイントを解説します。
「正社員として採用されたのに契約書が有期だった」ケース
求人票や面接で「正社員採用」と説明を受けていたのに、入社日当日に渡された書類が有期雇用契約だったという相談が多く寄せられます。この場合、説明と契約内容に不一致があるため、企業側に虚偽説明や説明義務違反が問われる可能性があります。特に人事部が「最初だけ有期」「本採用後は無期にする予定」など曖昧な説明をしていたケースでは、紛争になりやすい傾向があります。
契約更新時の雇止めリスクと人事の運用実態
有期雇用契約は契約期間満了時に不利益が生じやすく、更新されない「雇止め」リスクが常に伴います。正社員と同じ仕事をしているにもかかわらず、有期契約を理由に更新を打ち切られるケースは珍しくありません。人事部が人員調整やコスト削減を目的に雇止めを行う企業もあり、更新条件が明示されていない場合は特に注意が必要です。
不合理な待遇差によるトラブル事例
同じ業務内容であっても、有期雇用という理由で昇給がない、ボーナスが出ない、福利厚生が限定されるなど不合理な待遇差が問題となることがあります。働き方改革関連法によって不合理な待遇差は禁止されていますが、企業の運用が追いついていないケースも多く、トラブルに発展しやすい部分です。給与や労働条件が無期社員と大きく異なる場合は早めに専門家に相談することが推奨されます。
【比較表】正社員・契約社員・有期雇用の違いをわかりやすく解説

正社員なのに有期雇用契約を提示された場合、まず理解すべきなのは「雇用形態ごとの違い」です。特に雇用期間、待遇、契約更新ルールの違いは労働条件の不合理性を判断するうえで重要な指標になります。ここでは正社員、契約社員、有期雇用社員を比較しながら、なぜ問題が発生するのかを整理します。
雇用期間と更新ルールの違い
正社員は無期雇用が前提で、雇止めが存在しません。一方で契約社員や有期雇用社員は契約期間が定められ、更新の可否は企業側の判断に左右されます。正社員として採用されたのに契約期間が設定されると、事実上「契約社員と同じ扱い」になり、雇用の安定性が大きく損なわれます。
給与・待遇・福利厚生の不合理性の判断
同じ職務内容であるにもかかわらず、有期雇用契約を理由に昇給・賞与・手当・休暇制度が制限されるケースは多く、不合理な待遇差として問題となることがあります。働き方改革関連法では不合理な待遇差が禁止されており、業務内容が正社員と変わらない場合は改善を求めることが可能です。
契約期間の上限と企業が設定する理由
企業が契約期間を設定する理由には、人件費の管理や人員調整、部署編成の柔軟化などがあります。しかし、正社員採用と言われて入社したにもかかわらず有期契約を渡される場合、企業の内部事情で雇用を調整している可能性が高く、労働者が不利益を受けるリスクがあります。契約期間の上限が不自然に短い場合は特に注意が必要です。
正社員なのに有期雇用契約を提示されたときの正しい対処法

正社員として採用されたはずなのに有期雇用契約を渡された場合、まず重要なのは「事実確認」と「契約内容の把握」です。企業側の説明不足や不合理な契約変更は、労働契約法上の問題となる可能性があります。このセクションでは、実際に何を確認し、どう対応すべきかを弁護士の視点から整理して解説します。
まず確認すべき契約書・雇用期間・就業規則のポイント
最初に確認すべきなのは、雇用契約書に記載された契約期間、契約更新条件、労働条件明示書の内容です。求人票や説明内容と異なる場合は、企業側に説明義務違反が疑われます。また、就業規則に有期雇用の取り扱いが記載されているかも重要で、規定がない場合はさらに問題が大きくなります。
人事部との交渉方法と契約解除を求められるケース
契約内容に納得がいかない場合、人事部に説明を求めることができます。特に「正社員採用と聞いていた」「契約期間の説明を受けていない」という点は明確に伝えるべきです。また、企業側が一方的に有期雇用契約へ変更しようとする場合は、労働契約法違反となる可能性が高く、交渉では契約解除や条件修正を求められるケースもあります。
働き続ける場合と退職すべき場合の判断基準(弁護士が解説)
企業の説明が不十分であったり、待遇が不合理な状態が続くのであれば、無理に働き続ける必要はありません。契約更新のリスクが高い場合や、雇止めの可能性がある場合は、早めに転職を検討する選択肢もあります。反対に、明確な説明があり本採用後に無期雇用へ移行する仕組みが整っている企業であれば、働き続けるメリットもあります。最終的には契約内容、人事の運用、会社の対応姿勢を総合的に判断する必要があります。
無期転換ルールとは?5年ルールで正社員の権利を守る方法

有期雇用契約で働く場合に必ず知っておくべき制度が「無期転換ルール」です。これは労働契約法第18条で定められた権利で、一定の条件を満たすことで労働者が無期雇用に転換できる制度です。有期契約で雇用が不安定な正社員扱いの労働者にとって、雇止めを防ぎ、雇用を安定させるための重要な仕組みとなります。
無期転換申込権が発生する条件と期間の計算方法
無期転換申込権は「有期雇用契約が通算5年を超えたとき」に発生します。例えば1年契約を5回更新した場合、更新後に労働者が申し込むことで無期雇用へ転換できます。注意すべきなのは、契約期間の途中で申し込むのではなく「契約更新された後」に申込権が生じるという点です。企業側は申込権を拒否できず、法律で強く保護されています。
クーリング期間とは?企業が悪用しがちなポイント
クーリング期間とは、契約と契約の間に一定期間をあけることで「通算契約期間をリセットできる」とされる期間のことです。しかしこれは濫用されやすく、労働者が無期転換できないよう企業が意図的に短期契約を挟むケースが問題となっています。厚生労働省のガイドラインでは、クーリング期間の適用には厳格な要件があり、不自然な運用は違法と判断される可能性があります。
無期転換を申し込む最適なタイミング
無期転換の申し込みは契約更新後に行う必要がありますが、実際には「更新直前に企業から雇止めを示唆される」ケースもあります。こうした場合でも、通算5年を超えていれば申込権が認められる可能性が高く、企業の一方的な判断に従う必要はありません。契約更新のタイミングに不安がある場合は、早めに専門家へ相談することで権利を確実に守ることができます。
有期雇用契約に納得できず退職を考える方へ|弁護士法人みやびの退職代行

正社員として働き始めたにもかかわらず、有期雇用契約を提示されたり、不合理な待遇差に悩んでいる場合、無理に働き続ける必要はありません。契約期間や雇用条件に疑問があるときは、法的に正しい手順で解決することが重要です。弁護士法人みやびは、有期雇用契約に関するトラブルや即日退職の相談を数多く扱っています。
有期雇用契約でも即日退職が可能な理由
有期雇用契約でも、法的根拠に基づいて退職を申し出ることで即日退職が認められるケースがあります。特に労働条件の明示違反や説明不足、不合理な待遇差が疑われる場合は、弁護士が企業側へ交渉することで安全に手続きを進めることができます。民間の退職代行では対応できない法的交渉も、弁護士であれば可能です。
弁護士法人みやびが選ばれる3つの理由
1. 法律に基づく正式な通知と交渉ができる
2. 有期雇用契約や無期転換ルールに関する専門的な知識がある
3. 依頼当日からの即日対応が可能で、在籍中のトラブル防止力が高い
弁護士が直接対応するため、会社からの嫌がらせや不当要求を確実に遮断できます。
無料相談から退職完了までの流れ(最短当日対応)
退職の流れはシンプルです。まずLINEまたはメールで無料相談を行い、状況をヒアリングします。その後、正式に依頼を受けて企業へ連絡し、退職日や貸与品返却の方法を調整します。多くのケースでは依頼当日に出社不要となり、書類の受け取りもすべて郵送で完了します。初めての方でも安心して利用できるよう、完了まで弁護士が全てサポートします。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。
正社員なのに有期雇用契約に関するよくある質問(FAQ)
正社員なのに有期雇用契約を提示された際に、多くの方が疑問を抱くポイントをまとめました。労働契約法・無期転換ルール・退職や契約変更の可否など、実務的な観点から分かりやすく回答します。
Q1. 正社員なのに有期雇用契約にされるのは違法ですか?
「正社員」という呼称には法律上の定義がありません。そのため、企業が有期雇用契約で採用しつつ「正社員」と説明すること自体は直ちに違法ではありません。ただし、無期雇用だと誤認させるような説明をしていた場合は不当表示として争える可能性があります。
Q2. 試用期間中だから有期契約でも問題ないと言われました。正しいですか?
試用期間を有期契約にすること自体は許容されていますが、更新拒否(雇止め)の基準は無期雇用より厳しく審査されます。試用期間を理由に不当に雇止めされた場合は争える可能性があります。
Q3. 無期転換ルールは正社員にも適用されますか?
適用されます。有期雇用で通算5年を超えて働いた場合、従業員から申込をすれば無期雇用に転換できます。企業が「正社員扱いだから関係ない」と説明しても、契約書が有期であれば対象となります。
Q4. 契約書の雇用期間が短く、更新されるか不安です。どう対応すべきですか?
契約社員として扱われる場合、雇止めリスクが生じます。更新基準や契約期間の明示は企業の義務であり、不明瞭な場合は書面で確認することが重要です。曖昧な運用が続く場合は労働局や弁護士への相談を推奨します。
Q5. 正社員として採用と言われて入社したのに、書面では有期契約でした。辞めたい場合は即日退職できますか?
可能です。有期雇用契約でも、事実上の労務提供が困難な場合や企業側の説明に問題がある場合、即日退職が認められるケースがあります。弁護士型退職代行であれば法的根拠に基づき安全に手続きできます。
Q6. 有期雇用契約でも、賞与や昇給は受けられますか?
可能です。ただし企業の就業規則や人事制度によって扱いが異なります。不合理な待遇差がある場合は労働契約法20条に基づき是正を求められることがあります。
Q7. 正社員なのに有期雇用契約を続けるメリットはありますか?
メリットは限定的です。キャリア形成や評価制度が曖昧になりやすく、雇止めリスクも残ります。長期的には無期転換や雇用形態の見直しを交渉する方が安定性の面で優れています。