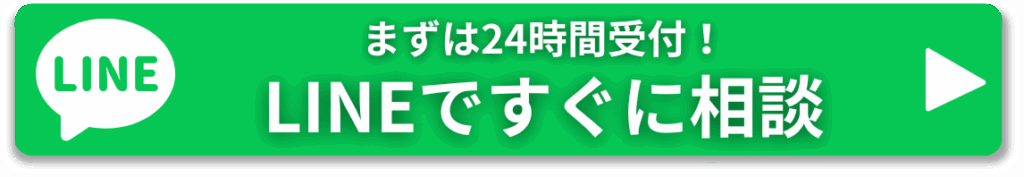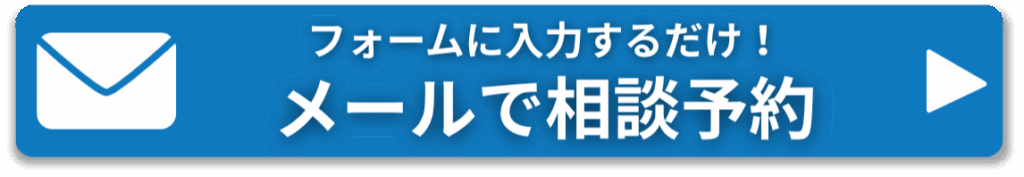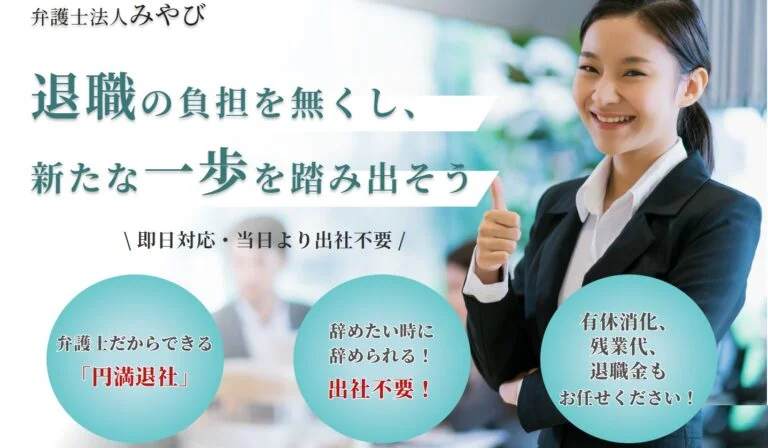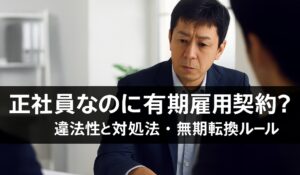退職代行で損害賠償請求された事例とリスク解決を弁護士が解説

退職代行サービスは、近年多くの労働者が利用するようになった新しい退職手段です。職場での人間関係や精神的な負担が大きい場合、第三者に任せて退職手続きを進められる点が注目されています。
しかしその一方で、適切に対応しなければ「損害賠償請求」といった思わぬトラブルに巻き込まれるケースも存在します。特に民間の退職代行業者を利用した場合、弁護士のような法的権限を持たないため、トラブルを未然に防げないことも少なくありません。
ここでは退職代行を利用した際に損害賠償請求されるリスクやその実例をもとに、弁護士に依頼すべき理由や、確実で安全な退職の方法について詳しく解説します。
弊所「弁護士法人みやび」は退職代行サービスを古くから提供する老舗の法律事務所です。すべての案件に対して弁護士が直接介入するので、損害賠償請求のトラブルにも対応可能です。また、「うちの会社は退職代行を使うと理不尽な請求をしてくるかも」という場合も、弊所弁護士に依頼することあらゆる請求を事前に退けることができます。
まずはLINE無料相談よりお問い合わせください。
この記事で分かること
- 退職代行利用後に損害賠償請求される2つの事例紹介
- 民間の退職代行業者に依頼すると損害賠償請求されるリスクがある
- 損害賠償請求が不安な人は弁護士の退職代行を利用すべき
- 「弁護士法人みやび」ではLINEによる無料相談窓口実施中
退職代行の後に損害賠償請求される事例はある?弁護士が解説

企業への退職の手続きを代行業者が代理する退職代行サービスですが、適切ではない辞め方や強引な手段を用いた交渉、違法性の高い業者へ代行業務を依頼してしまったことにより、実際に依頼者が損害賠償請求される事態に陥るケースがあります。
以下では退職代行を使った従業員が退職後に会社から損害賠償請求されるケースを紹介します。
1.引き継ぎをまったくしないで強引に退職したことで損害賠償された
退職代行業者によっては依頼者が「引き継ぎをしたくない」という言葉を鵜呑みにし、すべての会社からの引き継ぎ要求を拒否するところもあるようです。法律知識の浅い民間の退職代行業者は、「民法627条」を盾に、2週間後に強制的に辞めることができると考えているところが多いですが、法的に退職完了したあとに、会社から仕返しのように合法的に損害賠償請求される事例も相次いでいます。
基本的に引き継ぎの有無は法で決められていませんが、依頼者が重要なアポイントやプロジェクトなどの引き継ぎを放棄することで直接的に会社が損害を負う場合は、従業員の損害賠償支払いが認められるケースもあります。引き継ぎの有無は法律知識の深い弁護士に決めてもらうのが良いでしょう。
2.民間業者に依頼して会社からの連絡を無視・LINEブロックする
もう1つ、退職代行を使った後で会社から損害賠償請求されるケースがあります。それが「会社からの連絡を無視する」行為です。こちらも無視したことにより、職場の後任が仕事ができず、取引先からの契約が打ち切られてしまう、という可能性もあります。
相談者の中には、退職代行に依頼すればその日から会社からの連絡を無視したり、LINEからの通知をブロックしてもいいと考える人がいますが、それは「弁護士」の退職代行を利用した時です。弁護士の退職代行を利用すると、弁護士が正式な依頼者の「代理」となるので、弁護士担当者が受け皿となることができますが、民間の退職代行業者はそれができません。
退職代行を利用して企業に損害賠償される例と就業規則の関係性

退職代行を利用して退職した後、企業側から損害賠償請求を受けるケースの多くは、「就業規則に違反した」とみなされる行為が関係しています。就業規則は各企業が定めたルールであり、退職に関する手順や義務も明記されています。
例えば、「退職の〇日前までに申告すること」や「業務引き継ぎの完了を義務とする」といった内容が盛り込まれている場合、それを無視して突然の退職を実行すると、企業側はルール違反として責任追及を行う可能性があります。引き継ぎを怠ったことにより業務に支障が出た場合は、就業規則に基づいた損害賠償請求という形で対応されることもあります。
退職代行を使えば形式上の退職手続きは完了しますが、それと損害賠償請求とは別問題となることも認識が必要です。
引き継ぎ拒否が損害賠償の原因になる理由
企業は従業員に対して業務の継続性を担保するため、引き継ぎを前提とした退職を期待しています。
そのため、突然の退職や一切の引き継ぎを拒否した行為により、取引先との契約違反や顧客対応の遅れなどが生じれば、企業は損害を被ったと主張できます。
法律上、引き継ぎ義務が明確に定められているわけではありませんが、実務的には「信義則(しんぎそく)」に基づいて、誠実な退職対応が求められます。
この誠実な対応が欠けた場合に、「不法行為」としての損害賠償が請求されるリスクが発生します。
企業側の就業規則と法的な交渉のポイント
企業が損害賠償請求を行う根拠として最も多いのが、「自社の就業規則に反した退職手続き」です。
特に大手企業や上場企業では、法務部門を通じて本格的に損害賠償請求に踏み切ることもあります。
こうした状況下では、退職者自身が会社と直接交渉するのは非常に困難です。そのため、退職代行を弁護士に依頼し、就業規則と照らし合わせた上で合法的に対処してもらうのが最善の方法です。
ただし、基本原則、法律は就業規則の上に位置するため。弁護士であれば、企業の主張に法的反論を加え、損害請求の正当性を精査することで、過剰な請求や不当な圧力を防ぐことができます。
労働組合加盟の退職代行でも損害賠償リスクは避けられない。後悔する人も多い

労働組合加盟の退職代行サービスは、法律上「団体交渉権」を持っており、企業との交渉が可能です。
このため、弁護士以外でも一定の交渉が許されるというメリットがあります。
しかし、すべてのケースで安全とは限りません。労働組合が対応できるのは「団体交渉」に関する範囲に限られており、個別の損害賠償問題や就業規則に関する法的判断には対応できないことが多くあります。
また、労働組合加盟の退職代行業者で働く従業員は、民間企業と変わらないサラリーマンです。法知識は当然ありませんし、経験や交渉力に差があるため、会社との対応で不十分なサポートを受けてしまったり、退職を優先するあまり、常識を超えた会社側の要求を呑んで妥協してしまうケースも存在します。
最終的に「やはり弁護士にしておけば良かった」と後悔する利用者も少なくありません。
損害賠償トラブルを完全に防ぐには弁護士が最適
損害賠償のリスクをゼロにするためには、やはり法律の専門家である弁護士による対応が最も確実です。引き継ぎ拒否や企業側からの不当な請求が発生した場合でも、弁護士であれば法的根拠をもって企業と交渉することが可能です。
労働組合の退職代行は費用面で魅力的に見えるかもしれませんが、万が一のトラブルや裁判リスクを考慮すると、弁護士に依頼するほうが「安全性」と「安心感」の面で大きく勝ります。損害賠償請求されて、支払いが必要になったときの賠償金額や精神的疲労を考慮すると、退職代行の選び方は弁護士一択と言えるのではないでしょうか。
損害賠償のリスクは「民間の退職代行業者」に依頼したとき

上記では退職代行サービスを利用したことで、会社から損害賠償請求される事例とリスクを紹介しました。このことからも分かるように、基本的に会社が損害賠償を請求するケースのほとんどは、相談者が依頼した退職代行が民間業者のケースとなります。
弁護士であれば法律に則って確実な退職を遂行するため、会社が損害賠償請求を従業員にする根拠を与えません。民間業者の退職代行サービスは確かに弁護士よりも往々にして安価ですが、「退職」という法的手続きを一般の企業に任せるのは大きなリスクが付きまとうことが分かります。
損害賠償の根拠として使われる法律と企業側の主張
企業が損害賠償を主張する際、根拠となるのが「民法709条(不法行為による損害賠償)」や「債務不履行に基づく損害賠償請求」です。
従業員の突然の退職によって業務が停止し、明確な損害が生じた場合には、裁判にまで発展するケースもあります。ただし、実際に退職者が賠償金を支払うまでに至ることは少なく、多くは弁護士の交渉や示談で解決します。
そのため、最初から弁護士に退職代行を依頼しておけば、不要なリスクを避けることが可能となるのです。
退職代行サービスは弁護士に依頼すべき。損害賠償請求も確実に回避

ここまで説明したことからも分かるように、退職代行サービスは、民法627条の「労働者は退職の意思を会社に伝えた2週間後に退職できる」ことを基本原則として退職交渉を会社と行います。しかし、やり方を間違えたり、弁護士資格のない人間が介入してしまうと、「退職はできたけど、後日会社から損害賠償請求される」トラブルに陥る可能性があります。
一方で弁護士に依頼した相談者が退職代行完了後に損害賠償請求されたとしても、実際に支払いが命じられた、という事例はこれまで聞いたことがありません。弁護士であればそもそ損害賠償を請求されるリスクがある指示を依頼者に出すことはありません。また、会社側も損害賠償の請求にあたって必要となる裁判費用と、実際支払いが命じられて受け取れる金額を考えると、到底つり合わないと考えるため、弁護士と事を構えることはほとんどありません。
損害賠償リスクを抑えるための具体的な対応方法
損害賠償リスクを最小限に抑えるには、退職の意思表示から引き継ぎ方法まで、すべてを計画的に進めることが大切です。
弁護士に依頼すれば、就業規則や契約内容をチェックしたうえで、退職までのスケジュールや必要な書類の作成を指導してくれます。
さらに、損害賠償を請求された際も、弁護士は訴訟回避のための交渉や、裁判での反論を準備することが可能です。
万が一に備えて、「引き継ぎ資料は作成する」「会社との連絡はすべて弁護士を通す」などの具体策を講じることが、有効なリスク回避になります。
損害賠償請求が不安な人は「弁護士法人みやび」に退職代行依頼を

今回解説したように、場合によっては従業員が退職代行を使って退職後に損害賠償請求を受ける可能性もあります。「うちの会社は社長のワンマンだから損害賠償請求してくるかも」、「損害賠償請求は怖いけど、引き継ぎはしたくない」といった人は、弊所「弁護士法人みやび」にご相談ください。
悪質な会社によっては、退職にあたり膨大な量の引き継ぎ強要させるところもあります。代行経験の浅い弁護士だと、「損害賠償請求されないようにすべての引き継ぎを行ってください」という担当者も少なくないようです。弊所在籍の弁護士は全員が退職代行の介入実績が豊富で、あらゆる業種・雇用形態にも対応経験があるので、会社の希望や反論を精査して、本当に必要な業務だけ引き継ぎするように交渉が可能です。また、引き継ぎにあたっても出社する必要なく、自宅で資料を作って郵送するよう手続きできます。
無料相談とLINE対応でスムーズに依頼可能
弁護士法人みやびでは、LINEを使った無料相談窓口を設けており、初めて退職代行を検討する方でも気軽に問い合わせできます。仕事が忙しい方でも、スマホから状況を伝えられるため、対面でのやりとりが難しい方にも最適です。
LINEで相談内容を送れば、見積もりや今後のスケジュール、法的に損害賠償請求を退けることが可能かどうかについても案内してくれます。依頼者様は精神的な負担を減らしながら、安心して退職までの準備を進めることができるでしょう。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。